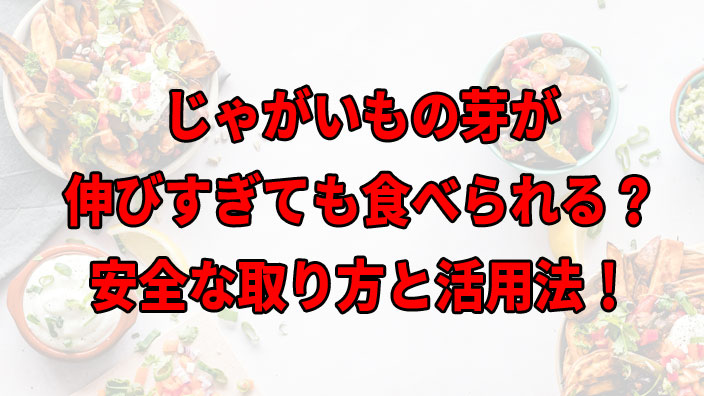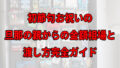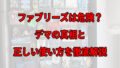買い置きしていたじゃがいもから、いつの間にかニョキニョキと芽が伸びていて驚いたことはありませんか?「これって食べても大丈夫なの?」「もったいないけど捨てるしかないのかな?」と不安になりますよね。
実は芽が伸びすぎたじゃがいもでも、正しく処理すれば安全に食べられますし、プランターで栽培して新しいじゃがいもを収穫することもできるんです。この記事では、伸びすぎた芽の危険性から安全な取り方、さらには栽培方法まで、詳しくわかりやすく解説していきます。
ほったらかしにしてたじゃがいも。
— マサミティ (@celica0310) May 22, 2012
芽が伸びすぎ。
食べれるやろか… pic.twitter.com/DgOptEKK
じゃがいもの芽が伸びすぎても食べられる?危険性について
じゃがいもの芽が伸びすぎていると、つい「もう食べられないかも」と思ってしまいますよね。でも実は、芽が長く伸びているからといって、じゃがいも全体が食べられなくなるわけではありません。
芽が伸びることで増える毒は、芽の部分と芽の根元に集中しています。つまり、じゃがいも本体の毒素が増えるわけではないんです。ただし、芽自体には注意が必要です。
じゃがいもの芽には「ソラニン」や「チャコニン」という天然毒素が含まれています。これらを食べてしまうと、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、頭痛、めまいといった中毒症状が起こる可能性があるため、絶対に食べてはいけません。
実際に私も以前、芽が3センチほど伸びたじゃがいもを発見したことがありました。最初は捨てようかと迷ったのですが、適切に処理すれば問題ないと知り、しっかり芽を取り除いて調理したところ、美味しく食べることができました。
じゃがいもの芽はどこまで伸びたら危険?見分け方のポイント
芽の長さよりも、じゃがいも本体の状態をチェックすることが大切です。
食べられるかどうかの判断基準は次の通りです。
食べられる状態
- 触ったときに硬さがある
- 表面にハリがある
- 切ってみて中身が変色していない
- 異臭がしない
食べてはいけない状態
- 触ると柔らかくなっている
- 表面がしわしわでブヨブヨしている
- 中身が茶色や黒く変色している
- 異臭がする
- 表面から汁が出ている
芽が10センチ以上伸びていても、じゃがいも本体がしっかり硬ければ、芽とその周辺をきちんと取り除けば食べられます。逆に、芽が短くても本体が傷んでいたら食べない方が安全です。
私の経験では、冬場に常温で保存していたじゃがいもは、春先になると急に芽が伸びやすくなりました。でも、硬さがあれば問題なく調理できたので、見た目だけで判断せず、必ず触って確認することをおすすめします。
じゃがいもの芽の毒「ソラニン」と「チャコニン」とは
じゃがいもの芽に含まれる毒について、もう少し詳しく知っておきましょう。
「ソラニン」と「チャコニン」は、じゃがいもが自分の身を守るために持っている天然の毒素です。これらは特に以下の部分に多く含まれています。
- 芽とその根元の部分
- 皮、特に緑色になった部分
- 日光に当たって緑化した部分
- 未熟で小さいじゃがいも
- 傷ついた部分
これらの毒素は加熱しても分解されません。つまり、煮ても焼いても揚げても、毒は残ったままなんです。だからこそ、調理前にしっかり取り除くことが重要になります。
ソラニンやチャコニンを大量に摂取すると、早ければ食後数分から数時間で症状が現れます。軽い場合は吐き気や腹痛程度ですが、重症化すると意識障害を起こすこともあるので、決して軽視できません。
伸びすぎた芽の正しい取り方|安全に食べるための5つのステップ
それでは、伸びすぎた芽を安全に取り除く方法を、順を追って説明していきます。
ステップ1:伸びた芽を手で折り取る
まず、長く伸びている芽を手でポキッと折って取り除きます。これをしておくことで、次のステップでピーラーや包丁が引っかかりにくくなります。
ステップ2:皮を厚めにむく
芽が出ているじゃがいもは、栄養が芽に取られて表面がしわしわになっていることが多いです。通常よりも厚めに、2〜3ミリほど皮をむきましょう。
ステップ3:芽の根元を深くえぐり取る
包丁の角やピーラーの芽取り機能を使って、芽が生えていた部分を深くえぐり取ります。目安は深さ5ミリほど。芽の根元には毒素が集中しているので、少し多めに取るくらいがちょうど良いです。
私はいつも、芽の周りを円錐形になるように、やや広めに深くえぐるようにしています。もったいない気もしますが、安全には代えられません。
ステップ4:緑色の部分もしっかり除去
皮をむいた後、緑色になっている部分が残っていないか確認してください。緑色の部分にもソラニンが含まれているので、見つけたら厚めに切り取りましょう。
ステップ5:水にさらす
処理が終わったら、10分ほど水にさらします。これで変色を防ぎ、表面に付着した毒素も洗い流すことができます。
この5ステップを守れば、芽が伸びたじゃがいもでも安全に調理できます。少し手間はかかりますが、食材を無駄にしないためにも、ぜひ実践してみてください。
芽が伸びたじゃがいもを使った調理方法と注意点
芽を取り除いたじゃがいもは、通常のじゃがいもと同じように調理できます。ただし、いくつか気をつけたいポイントがあります。
煮物やカレーに使う場合
芽が伸びたじゃがいもは、水分や栄養が芽に取られているため、通常のものよりも少し柔らかくなりやすい傾向があります。煮崩れしやすいので、煮込み時間は少し短めにするのがコツです。
私がカレーに使った時は、いつもより5分ほど早めに火を止めることで、ちょうど良い硬さに仕上がりました。
ポテトサラダやマッシュポテトに
芽が伸びたじゃがいもは、実は潰して使う料理に向いています。少し水分が少なくなっている分、ホクホクした食感になるんです。ポテトサラダやマッシュポテトに最適ですよ。
揚げ物には注意
フライドポテトやポテトチップスなど、高温で調理する場合は特に注意が必要です。緑色の部分が残っていると、揚げた後も毒素は残ります。緑色の部分がないか、念入りにチェックしてから調理しましょう。
調理時の最終チェックポイント
- 切った断面が変色していないか
- 異臭がしないか
- 柔らかすぎる部分がないか
これらを最終確認してから調理すれば、より安心して食べられます。
じゃがいもの芽を出さない保存方法|冷蔵庫と常温どっちが正解?
芽が伸びないように保存する方法を知っておけば、そもそも処理する手間がなくなります。
冷蔵庫での保存が基本的におすすめ
じゃがいもは5〜10度くらいの温度で保存すると、芽が出にくくなります。冷蔵庫の野菜室が理想的です。ただし、冷蔵庫で保存する場合は注意点があります。
冷蔵保存のコツは、じゃがいもを2〜3個ずつキッチンペーパーで包み、その上から新聞紙で覆うこと。これで適度な湿度を保ちながら、長期保存ができます。
常温保存する場合のポイント
夏以外の涼しい時期なら、常温保存も可能です。ただし、次の条件を守ってください。
- 直射日光が当たらない場所
- 風通しの良い場所
- 温度が15度以下の場所
- リンゴと一緒に保存する
リンゴから出るエチレンガスが、じゃがいもの発芽を抑制してくれるんです。私も試してみましたが、確かにリンゴと一緒に保存した方が、芽が出るまでの期間が長くなりました。
NGな保存方法
- ビニール袋に入れたまま
- 濡れたまま保存
- 日光が当たる場所
- 暖房の近く
これらは芽が出やすくなるだけでなく、傷みやすくもなるので避けましょう。
伸びすぎた芽のじゃがいもを植える方法|プランター栽培のコツ
食べるには芽が伸びすぎてしまったじゃがいも、実はプランターで育てて新しいじゃがいもを収穫することができます。捨てるのはもったいない、という方はぜひ挑戦してみてください。
必要なもの
- 芽が出たじゃがいも
- 深さ30センチ以上のプランター(容量20リットル以上が理想)
- 培養土
- 化成肥料(窒素・リン酸・カリウムが8:8:8のもの)
栽培の手順
- じゃがいもを半分か3分の1に切る(小さければそのまま)
- 切り口を2〜3日日陰で乾燥させる
- プランターに土を半分ほど入れる
- じゃがいもを切り口を下にして置く(間隔は15センチ以上)
- 土を5センチほどかぶせる
- たっぷり水をやる
育て方のポイント
芽が10センチほど伸びてきたら、「芽かき」という作業をします。太くて元気な芽を2〜3本だけ残して、あとは根元から抜き取ります。これをすることで、大きなじゃがいもが育ちます。
私が初めて栽培した時は、芽かきをせずにそのまま育ててしまい、小さなじゃがいもがたくさんできてしまいました。2回目は芽かきをしっかりしたところ、スーパーで売っているサイズのじゃがいもが収穫できて感動しました。
土寄せも忘れずに
じゃがいもが大きくなってくると、土から顔を出してしまうことがあります。そうすると日光に当たって緑化してしまうので、2週間に1回くらいのペースで、土を追加して盛り上げましょう。
収穫のタイミング
植え付けから3〜4ヶ月後、葉が黄色くなって枯れてきたら収穫の合図です。晴れた日に掘り起こしてみてください。
じゃがいもの芽が伸びる原因と予防策
そもそも、なぜじゃがいもから芽が出てしまうのでしょうか。原因を知ることで、予防もしやすくなります。
芽が出る3つの主な原因
- 温度が高い じゃがいもは15度以上の環境に置かれると、休眠状態から覚めて芽を出し始めます。特に春先は室温が上がりやすいので要注意です。
- 日光に当たっている 明るい場所に置いておくと、じゃがいもは「外に出た」と判断して、成長しようとします。光合成を始めようとして、芽を伸ばすんです。
- 湿度が高い 湿った環境では、じゃがいもが腐りやすくなるだけでなく、発芽もしやすくなります。
予防のための5つのポイント
- 購入時に新鮮なものを選ぶ(すでに小さな芽が出ているものは避ける)
- 冷暗所または冷蔵庫の野菜室で保存する
- リンゴと一緒に保存する
- 紙袋や新聞紙で包んで光を遮る
- 使う分だけ少量ずつ購入する
私は以前、安売りしていたからと5キロもじゃがいもを買ってしまい、使い切る前に半分以上から芽が出てしまった経験があります。それ以来、一人暮らしなので1キロずつ買うようにしています。少し割高かもしれませんが、結果的に無駄がなくなりました。
小さな子どもや高齢者がいる家庭での注意点
じゃがいもの毒素は、特に小さなお子さんや高齢者の方には影響が大きい場合があります。
子どもの場合の特別な注意
子どもは大人より体が小さいため、同じ量の毒素でも症状が出やすくなります。学校菜園で収穫したじゃがいもによる食中毒事例も報告されているので、特に注意が必要です。
- 未熟な小さいじゃがいもは使わない
- 皮ごと調理する料理は避ける
- 芽の処理は大人が必ず確認する
高齢者の場合の注意点
高齢になると、視力が低下して緑色の部分を見落としやすくなることがあります。また、包丁の扱いが不安定になり、芽の処理が不十分になる可能性も。
家族がいる場合は、芽の処理は一緒に確認し合うか、体調の良い人が担当するのが安心です。
もし症状が出たら
じゃがいもを食べた後、数時間以内に吐き気、腹痛、頭痛などの症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診してください。特に子どもの場合は、症状が軽くても念のため受診することをおすすめします。
カレーを作るために
— ねこのて。(胃もたれ) (@p6kLTNsqi612977) September 17, 2025
じゃがいも🥔の皮をむいていたら
じゃがいもの芽🌱がねこの手🐾の形だった🐾🥔 pic.twitter.com/y9UKMA5Awj
じゃがいも料理のおすすめレシピ|芽を取ったじゃがいもの活用法
芽をしっかり処理したじゃがいもは、美味しく調理できます。おすすめのレシピをいくつか紹介します。
ホクホクポテトサラダ
芽が伸びたじゃがいもは、水分が少し抜けてホクホクしているので、ポテトサラダに最適です。
- 芽を取り除いたじゃがいもを一口大に切る
- 柔らかくなるまで茹でる(通常より少し早めに)
- 熱いうちに潰して、マヨネーズと塩コショウで味付け
- きゅうり、ハム、ゆで卵などを混ぜる
簡単じゃがいもバター
私の一番のお気に入りレシピです。
- じゃがいもを皮をむいて一口大に切る
- 電子レンジで5〜6分加熱
- バターと醤油を絡めて完成
シンプルですが、じゃがいもの甘みが引き立って本当に美味しいです。
じゃがいものガレット
- じゃがいもを細切りにする
- 塩コショウをして、フライパンで平たく広げる
- 両面をカリッと焼く
- チーズを乗せても美味しい
外はカリカリ、中はホクホクの食感が楽しめます。
よくある質問
Q1. じゃがいもの芽が1センチ程度伸びている場合、食べても大丈夫ですか?
はい、問題なく食べられます。芽の長さよりも、じゃがいも本体の状態が重要です。触ったときに硬さがあり、変色や異臭がなければ大丈夫です。ただし、芽とその根元を深さ5ミリ程度しっかりえぐり取ること、緑色になった皮も厚めにむくことが絶対条件です。1センチの芽なら、包丁の角やピーラーの芽取り機能で簡単に処理できますよ。
Q2. 冷蔵庫で保存するとじゃがいもが甘くなると聞きましたが本当ですか?
本当です。じゃがいもは低温環境に置かれると、寒さから身を守るためにでんぷんを糖に変えます。そのため、冷蔵庫で長期保存すると甘みが増すんです。これ自体は問題ありませんが、甘くなったじゃがいもを高温で調理すると、アクリルアミドという物質が生成されやすくなる可能性があります。冷蔵保存したじゃがいもは、煮物など比較的低温の調理法で使うことをおすすめします。
Q3. じゃがいもの芽を取り忘れて食べてしまいました。どうすれば良いですか?
まず落ち着いて、体調に変化がないか観察してください。少量であれば、すぐに症状が出ないこともあります。食後2〜3時間は特に注意が必要です。吐き気、腹痛、頭痛、めまいなどの症状が少しでも出た場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。特に子どもや高齢者の場合は、症状が軽くても念のため相談することをおすすめします。何も症状が出なければ、次回から気をつけるようにすれば大丈夫です。
Q4. 緑色になったじゃがいもは、皮をむけば食べられますか?
緑色の部分には毒素が含まれているため、皮をむいただけでは不十分な場合があります。緑色になった部分は、通常より厚め(3〜5ミリ程度)に切り取る必要があります。表面だけでなく、切ってみて中まで緑色になっている場合は、その部分も含めて大きめに取り除いてください。全体的に緑色が広がっている場合は、もったいないですが食べずに栽培に回すか、処分することをおすすめします。
Q5. スーパーで買ったじゃがいもでも栽培できますか?
できますが、おすすめはしません。食用のじゃがいもは、ウイルス病に感染している可能性があります。食べる分には全く問題ありませんが、栽培すると収穫量が極端に少なくなったり、全く収穫できないこともあります。栽培を楽しむなら、園芸店で売っている「種いも」を使う方が確実です。ただし、家庭で余ってしまった芽が出たじゃがいもを「試しに植えてみる」程度なら、ダメ元で挑戦してみるのも面白いですよ。私も食用のじゃがいもで栽培したことがありますが、数個は収穫できました。
Q6. じゃがいもの芽かきで取った芽は、また植えられますか?
残念ながら、芽かきで取った芽だけを植えても育ちません。じゃがいもは芋の部分に栄養を蓄えているため、芽だけでは十分な栄養がなく、成長できないのです。芽かきで取った芽は、堆肥として利用するか、処分してください。新しくじゃがいもを育てたい場合は、芋の部分が付いた状態で植える必要があります。
「ポテト」の人気商品をレビュー件数順に楽天でチェック!まとめ
じゃがいもの芽が伸びすぎていても、正しく処理すれば安全に食べられます。大切なのは、芽とその根元を深さ5ミリほどしっかりえぐり取ること、緑色の皮も厚めにむくこと、そしてじゃがいも本体の状態をチェックすることです。
食べるのが不安な場合は、プランターで栽培して新しいじゃがいもを収穫する方法もあります。3〜4ヶ月後には、新鮮なじゃがいもが手に入りますよ。
何より大切なのは、芽が出る前に適切に保存すること。冷蔵庫の野菜室で保存したり、リンゴと一緒に冷暗所に置いたりすることで、芽が出にくくなります。
じゃがいもは本当に便利な食材です。正しい知識を持って、無駄なく安全に活用していきましょう。