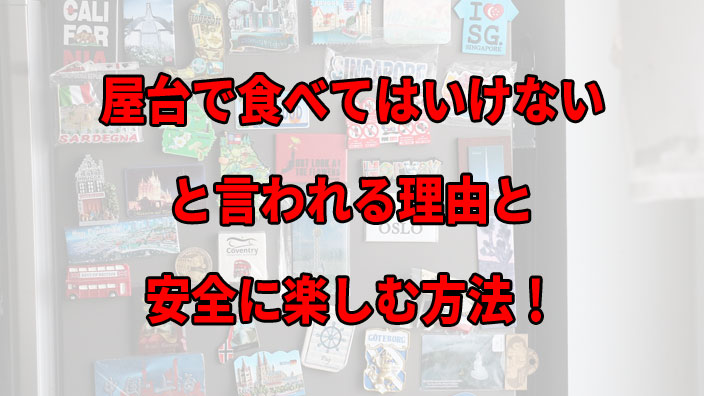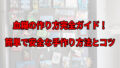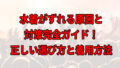お祭りや花火大会で見かける屋台の食べ物。香ばしい匂いに誘われてついつい買いたくなりますよね。でも「屋台の食べ物は危ない」という話を聞いたことはありませんか。この記事では、屋台の食べ物に関する真実と、安全に楽しむための方法を詳しく解説します。
台湾 屋台祭🇹🇼 in みなとみらい pic.twitter.com/RYTqRxyh2g
— Eiichiro🌿 (@Eiichiros5003) November 8, 2025
屋台で食べてはいけないと言われる主な理由
衛生管理が不十分な環境で調理されている
屋外で調理する屋台は、室内の飲食店に比べて衛生面の管理が難しく、食べ物が雑菌やウイルスに汚染されやすい環境にあります。保健所の許可を得ている屋台でも、野外という環境上、完璧な衛生管理は困難です。
具体的には、次のような問題があります。調理器具を洗う水が十分に確保できない、ほこりや虫が入りやすい、手洗いが十分にできないなど、室内の飲食店では当たり前にできることが、屋台では難しいのです。
夏祭りに行った時のことです。たこ焼き屋の列に並んでいると、お店の人がお金を触った後、手も洗わずそのまま食材を触っているのを見てしまいました。さすがにその店では買うのをやめましたね。
食材の鮮度や保管状態に問題がある
前日に使い切れなかった食材を翌日に繰り越して使う可能性が高く、保冷環境も十分でないため、食材の劣化が進んでいる可能性があります。
朝から晩まで営業している屋台では、食材が常温で長時間置かれることも珍しくありません。特に夏場は気温が高いため、細菌が繁殖しやすい環境になっています。クーラーボックスに入れていても、頻繁に開け閉めすることで温度が上がってしまうのです。
食材の原産地や品質がわからない
屋台の原価は1割程度と言われており、できるだけ安く食材を仕入れることが基本となっているため、品質の低い食材を使用している可能性があります。
通常の飲食店では産地や品質を確認できますが、屋台ではそれが難しいです。コストを抑えるため、品質よりも価格を優先して食材を選んでいるケースも多いのが現実です。
調理者の衛生意識のばらつき
屋台を運営する人の中には、飲食業の経験が浅い人や、衛生管理の知識が不足している人もいます。お金を触った手で調理する、使い捨て手袋を長時間つけっぱなしにする、といった光景を見かけることもあります。
お祭りで働いている友人から聞いた話ですが、忙しい時間帯は「焼けば大丈夫」という考えで、細かい衛生管理まで気を配れないこともあるそうです。
屋台で起きやすい食中毒の種類
屋台や露店で起きやすい食中毒には、O-157、ノロウイルス、カンピロバクター、黄色ブドウ球菌などがあり、感染すると腹痛、下痢、嘔吐、吐き気といった症状が出ます。
O-157による食中毒
2014年8月、静岡県の花火大会の屋台で売られていた浅漬けの冷やしきゅうりで集団食中毒が発生し、腸管出血性大腸菌O157に感染して8名もの死者が出ました。
この事件は屋台の食中毒リスクを世間に知らしめる大きなきっかけとなりました。特に小さな子どもや高齢者は、食中毒にかかると重症化しやすいため、十分な注意が必要です。
黄色ブドウ球菌による食中毒
黄色ブドウ球菌は人の手や皮膚に常在している菌です。手洗いが不十分な状態で調理すると、食べ物に菌が付着し、増殖した菌が毒素を作り出します。この毒素は加熱しても消えないため、非常に厄介です。
前日に自宅で焼いたクレープ生地を常温で保管し、翌日使用したことで黄色ブドウ球菌による食中毒が発生した事例もあります。
特に注意すべき屋台の食べ物
冷やしきゅうり(浅漬け)
屋台で売られているきゅうりはほとんどが浅漬けで、塩分が少ないため雑菌が繁殖しやすく、氷の上に並べているだけの店も多く、氷が解けて温度が上がった状態で放置されている場合もあります。
静岡市の保健所は食中毒事件後に「冷やしキュウリは販売許可がおりない商品」と説明しており、かなりハイリスクな食べ物です。
焼き鳥・牛串などの肉類
牛串や焼き鳥などは屋台の定番メニューですが、食中毒がおきやすい食べ物のひとつで、出店者が手袋をせず素手で食肉を扱っている店は特に注意が必要です。
生肉にはカンピロバクターなどの食中毒菌が付着している可能性が高いです。十分に加熱されていない、または調理後に素手で触れることで菌が付着するリスクがあります。
前日からの持ち越し食材を使った食べ物
焼きそばやイカ焼きなど、前日の残り食材を使っている可能性がある食べ物も要注意です。鉄板に残したまま一晩置いた焼きそばを、翌日炒め直して提供しているという話も聞きます。
かき氷
かき氷の氷の保管状態が悪いと、細菌が繁殖している可能性があります。また、シロップの容器やスプーンなどの衛生管理も気になるところです。
以前、かき氷の氷が魚屋から仕入れたもので、魚の血やウロコが付いていたという話を聞いて驚きました。本当かどうかは分かりませんが、そういう可能性もゼロではないのかもしれません。
クレープやわたあめ
わたあめを買おうと並んでいた時、お店の人が袋を開けるために息を吹き込んで開けているのを見て、その店で買うのをやめたという体験談があります。
生クリームを使ったクレープは、保冷が不十分だと特に危険です。保健所の指導により、屋台では生クリームの使用は控えるよう言われていますが、すべての店が守っているとは限りません。
屋台の食べ物を安全に楽しむための7つのポイント
営業許可証が掲示されているか確認する
保健所に届けを出して発行された営業許可証は、屋台の目立つところに掲示しなければいけないため、営業許可証をチェックしましょう。
許可証があれば最低限の衛生基準は満たしているということになります。許可証が見当たらない屋台では、買うのを控えた方が無難です。
調理している様子をよく観察する
購入前に、次のポイントを確認してみてください。
- 使い捨て手袋を使用しているか
- お金を触る人と調理する人が分かれているか
- 手指のアルコール消毒をしているか
- 調理器具が清潔に見えるか
- 食材が冷たい状態で保管されているか
花火大会で焼きそばを買った時、お店の人が手袋を変えながら丁寧に調理しているのを見て、この店なら安心だと感じました。やはり見た目の清潔感は大事です。
十分に加熱されている食べ物を選ぶ
屋台は鉄板などで加熱する食品が多いですが、これは保健所が「提供する食品は客への提供直前に加熱を行ってください」と指導している結果です。
たこ焼き、焼きそば、フランクフルトなど、しっかり火が通っている食べ物の方が、食中毒のリスクは低くなります。生野菜や半生の食べ物は避けるのが賢明です。
できるだけ早い時間帯に購入する
生肉などの食材は午前中の早い時間帯に購入するのがよく、日中の暑い時間以降は避けるべきです。
朝や昼の早い時間なら、食材もまだ新鮮で、調理器具も比較的清潔な状態です。夕方以降、特に夏場は食材の劣化が進んでいる可能性が高くなります。
その場で食べる
屋台で購入した食べ物は、できるだけその場で食べるようにし、残ったものは捨てる覚悟でいた方が安心です。
持ち帰って時間が経つと、細菌が増殖するリスクが高まります。温かいまま密閉された容器の中は、細菌にとって絶好の繁殖環境になってしまうのです。
地元の飲食店や町内会が運営する屋台を選ぶ
地元の飲食店や町内会、婦人会が運営する屋台は、衛生管理がしっかりしている傾向があり、地域の信頼を得て運営しているため、安心して食べられる可能性が高いです。
普段から営業している飲食店が出している屋台なら、評判を気にするため衛生管理も意識しているはずです。看板やのぼりに店名が書いてあるかチェックしてみましょう。
見た目や匂いに異変を感じたら食べない
食べ物に変な匂いや色、味がある場合は食べるのをやめましょう。特に、りんご飴のりんごが黒ずんでいる、焼きそばが糸を引いているなどの場合は、品質に問題がある可能性があります。
少しでも「おかしいな」と感じたら、食べるのをやめる勇気も必要です。もったいないと思うかもしれませんが、食中毒になるリスクを考えれば、安い投資だと言えます。
屋台といえば焼きそばとチーズドック😋
— MUW.@紫&HM (@KAZM670518) November 8, 2025
ここはお酒の種類も良いよ🥃🎶 pic.twitter.com/bDsVlEH6Rj
屋台の食べ物を避けた方がいい人
小さな子どもや高齢者
子どもやお年寄りは食中毒が重症化しやすいので特に注意が必要で、小学校の高学年になるまでは食べさせないなど、決めてもいいかもしれません。
子どもの免疫力は大人より低いため、少量の菌でも食中毒を起こす可能性があります。特に3歳以下の乳幼児には、屋台の食べ物は避けた方が無難です。
妊娠中の方
妊娠中は免疫力が低下しているため、食中毒にかかりやすくなります。また、一部の食中毒菌は胎児に影響を及ぼす可能性もあるため、できるだけ避けた方が安心です。
持病がある方や体調が悪い方
糖尿病や腎臓病など、免疫力が低下する病気を持っている方は、食中毒のリスクが高くなります。また、体調が悪い時も抵抗力が落ちているため、屋台の食べ物は控えましょう。
屋台の食べ物を食べずに祭りを楽しむ方法
家で食べてから出かける
空腹で行くと食べたくなるので、家で食べてから出かけるとよく、メニューはお祭りでよく見かける焼きそばや焼きとうもろこし、お好み焼きなどにすると特別感があります。
ホットプレートで目の前で調理すれば、子どもも喜びますし、祭りの雰囲気も楽しめます。
食べ物以外の屋台で遊ぶ
お祭りには食べ物以外の屋台もあり、スーパーボールすくいや人形すくい、お面、ヨーヨーつりなどがあります。
子どもは意外と遊びの屋台の方が楽しかったりします。食べ物は家で準備して、お祭りでは遊びをメインに楽しむのも一つの方法です。
コンビニで食べ物を買う
コンビニが店先で唐揚げやフランクフルトなどを売っていれば、そこで買うこともでき、コンビニの方が食材の保冷管理がしやすいため、屋台よりは食中毒のリスクが低いでしょう。
お祭り会場の近くにコンビニがあれば、そこでホットスナックを買って食べ歩くのもいいですね。少しお祭り気分は減りますが、安全性は格段に高くなります。
屋台のルールと保健所の指導
1店舗1品目のルール
簡易テントの屋台は1軒につき1品目しか提供できないというルールがあります。これは衛生管理を徹底するための保健所の指導によるものです。
複数のメニューを扱うと、食材の管理や調理工程が複雑になり、衛生管理が不十分になるリスクが高まるからです。
仕込み作業の制限
屋台でキャベツを刻むなど仕込み作業はできず、原材料のカットや焼き鳥の串刺しなどの仕込み行為は、調理室等の衛生的な場所で当日行うよう保健所が指導しています。
屋外での仕込み作業は、ほこりや虫の混入、食材の汚染などのリスクが高いためです。
生ものの提供制限
屋台のクレープは生クリームを使っていなかったり、握り寿司や刺身を提供する屋台がないのは、保健所が「生もの(刺身、寿司)、生クリーム、生野菜の提供はしないでください」と指導しているからです。
生ものは傷みやすく、食中毒のリスクが非常に高いため、屋台での提供は控えるよう指導されているのです。
調理時の衛生指導
調理する際は「爪は短く切り、マニキュアはつけない」「指輪、時計などは外す」「食品に直接触れないように使い捨て手袋を着用する」「調理をする人は、お金の受け渡しをしない」などが指導されています。
これらの指導が守られているかどうかが、安全な屋台を見分けるポイントになります。
屋台のこういうのって、まじ高いけど、美味いからつい買ってまうんよなぁ、、
— りうく (@callme_Riukkun) November 8, 2025
#屋台 #祭 #クレープ #大判焼き #初リプ・初絡み・時差リプ大歓迎 pic.twitter.com/IEqryKAeVe
屋台の食べ物に対する世間の声
SNSや口コミサイトには、屋台の食べ物に関する様々な意見が投稿されています。
ポジティブな意見としては「お祭りの雰囲気で食べるから美味しい」「年に数回のことだから気にしない」「楽しむことが大事」といった声があります。
一方で「一度お腹を壊してから食べられなくなった」「不衛生な調理を目撃してしまった」「子どもには絶対に食べさせない」という慎重な意見も多く見られます。
友人の中にも意見は分かれていて、「全然気にせず食べる」という人もいれば、「絶対に買わない」という人もいます。どちらが正しいというわけではなく、自分の価値観とリスクの許容度で判断するしかないのかもしれません。
よくある質問
Q1. 屋台の食べ物で食中毒になったことがある人はどのくらいいるの?
毎年縁日などの屋台で飲食をした方の中に食中毒を訴える人が結構います。ただし、軽度の症状の場合は報告されないことも多いため、実際の発生件数はもっと多い可能性があります。
食中毒の症状が出ても、「たまたま体調が悪かっただけ」と思い込んでしまうケースも多いです。数時間後に腹痛や下痢が起きても、屋台の食べ物が原因だと気づかないこともあります。
Q2. 屋台の食べ物は本当に全部危険なの?
すべての屋台が危険というわけではありません。保健所の許可を得て営業している屋台や、地元飲食店・町内会が運営する屋台は、衛生管理が徹底されている場合が多いです。
きちんと衛生管理をしている屋台も確実に存在します。ただし、見た目だけで判断するのは難しいため、先ほど紹介したチェックポイントを参考に、総合的に判断することが大切です。
Q3. 焼けば菌は死ぬから大丈夫じゃないの?
確かに加熱すれば多くの細菌は死滅します。しかし、黄色ブドウ球菌が作り出す毒素は加熱しても分解されません。また、加熱後に素手で触れることで再び菌が付着する可能性もあります。
「焼けば大丈夫」という考え方は、完全に安全とは言えないのです。
Q4. 子どもが屋台の食べ物を欲しがったらどうすればいい?
まずは家で同じようなメニューを作って満足させる方法があります。それでも欲しがる場合は、比較的リスクの低い食べ物(しっかり焼いたたこ焼きや、個包装のお菓子など)を選び、できるだけ衛生的な店で購入しましょう。
うちの姪っ子も屋台で買いたがるので、お祭り前日に家でたこ焼きパーティーをして、当日は我慢してもらうようにしています。意外とそれで満足してくれるものです。
Q5. 屋台で買った食べ物を持ち帰っても大丈夫?
屋台で購入した食べ物は、できるだけその場で食べるようにし、残ったものは捨てる覚悟でいた方が、後々の安心につながります。
特に夏場は細菌の増殖が早いため、時間が経つほど危険度が増します。どうしても持ち帰る場合は、保冷バッグに入れて、できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。ただし、それでも安全とは言い切れません。
Q6. お腹を壊しやすい体質なんだけど、屋台の食べ物は避けた方がいい?
はい、避けた方が無難です。普段からお腹を壊しやすい方は、胃腸が敏感だったり、免疫力が低下している可能性があります。屋台の食べ物はリスクが高いため、控えることをおすすめします。
Q7. 屋台の食べ物を食べて具合が悪くなったら、どこに苦情を言えばいい?
まずは最寄りの保健所に連絡しましょう。可能であれば、購入した屋台の場所や時間、食べた物の写真などを記録しておくと、調査がスムーズに進みます。症状がひどい場合は、すぐに医療機関を受診してください。
Q8. 地元の商店街が出している屋台なら安全?
地元の飲食店や町内会、婦人会が運営する屋台は、衛生管理がしっかりしている傾向があります。地域の評判を気にするため、一般的な屋台よりは信頼できる可能性が高いです。
ただし100%安全とは言い切れないので、やはり購入前に衛生状態をチェックすることは大切です。
「焼きそば」の人気商品をレビュー件数順に楽天でチェック!まとめ
屋台の食べ物には確かにリスクがあります。衛生管理が不十分な環境、食材の品質や保管状態の問題、調理者の衛生意識のばらつきなど、食中毒のリスクを高める要因が複数存在しています。
特に注意すべきなのは冷やしきゅうり、肉類、前日からの持ち越し食材を使った食べ物です。小さな子どもや高齢者、妊娠中の方、持病がある方は特に慎重になる必要があります。
しかし、すべての屋台が危険というわけではありません。営業許可証の確認、調理の様子の観察、十分に加熱された食べ物を選ぶ、早い時間帯に購入する、地元の飲食店が運営する屋台を選ぶなど、リスクを減らす方法はいくつもあります。
屋台の食べ物を完全に避けるのか、リスクを理解した上で楽しむのかは、個人の判断です。お祭りの雰囲気を楽しむことも大切ですが、自分や家族の健康を守ることも同じくらい大切です。
この記事で紹介したポイントを参考に、安全に屋台グルメを楽しんでくださいね。