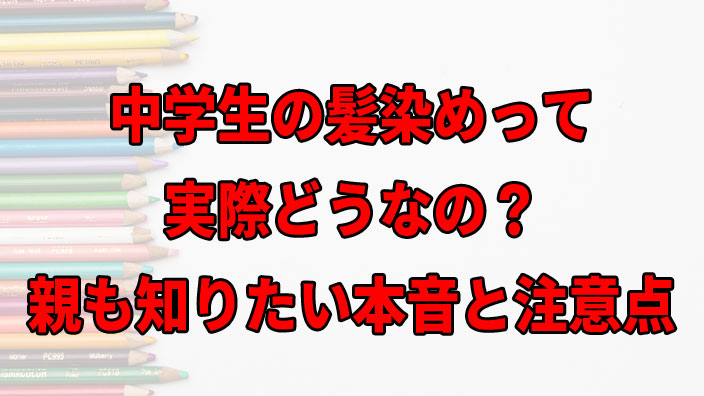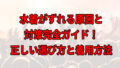最近、街中やSNSで髪を染めている中学生を見かけることが増えてきましたよね。校則が緩くなっている学校も出てきて、「うちの子も染めたいって言ってるけど、本当にいいのかな?」と悩んでいる保護者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、中学生の髪染めについて、健康面のリスクから校則の問題、親としての向き合い方まで、わかりやすく解説していきます。
中学生の髪染めが増えている背景とは?
校則の見直しで髪染めOKの学校が増加中
最近では「ブラック校則」の見直しが進んでいて、一部の学校では髪染めを認めるところも出てきています。例えば静岡市では、学校の校則について「社会通念に照らして合理的な理由が説明できる内容にする」というガイドラインを作成しました。
その結果、「授業や学校生活に支障がない頭髪」といった表現で、事実上頭髪自由にした中学校も少なくありません。実際に静岡市内の複数の中学校からは、茶髪に染める生徒が増えているという声も上がっています。
中学生が髪を染めたい理由って何?
中学生が髪を染めたいと思う理由は主に以下のようなものがあります。
おしゃれへの興味 思春期になると、自分をかっこよく・かわいく見せたいという気持ちが強くなります。髪色を変えることは、手軽に印象を変えられる方法の一つなんですね。
周りの友達の影響 友達が染めていると「自分も染めたい」と思うのは自然なこと。特に校則が緩い学校では、染めている子が増えるとその流れに乗りたくなる子も出てきます。
自己表現の手段として 「自分らしさ」を表現したいという気持ちから、髪色を変えたいと考える中学生もいます。個性を大切にしたいという思いの表れともいえるでしょう。
小学生?中学生?の子がお母さんと美容院に来てて子供は茶髪なんだけど、今って髪染めても良いの?🙄
— み😼 (@kateeneko1229) September 28, 2025
もしかして不登校?とか色々考える。
お母さんは腕にタトゥーあり…🙄
中学生の髪染めに潜む健康リスクを知っておこう
子どもの頭皮はとってもデリケート
実は中学生くらいの年齢では、まだ髪や頭皮が完全に成長しきっていません。大人と比べて子どもの髪や頭皮には以下のような特徴があります。
髪の毛の構造が未発達 中学生の髪の毛は、大人と比べてタンパク質が少なく細いのが特徴です。髪の表面を覆うキューティクルもしっかり重なり合っていないため、髪が柔らかくてダメージを受けやすい状態なんです。
頭皮の皮脂が少ない 頭皮を守る皮脂の量も大人より少ないため、外からの刺激にとても敏感。カラー剤のような刺激の強い薬剤が直接触れると、大人以上にダメージを受けやすいんですね。
カラー剤に含まれる危険な成分
ヘアカラー剤には、髪を染めるために必要だけど刺激の強い成分が含まれています。
過酸化水素 髪を脱色するために使われる成分ですが、皮膚や目に強い刺激を与えます。頭皮に残ると炎症の原因になることも。
ジアミン(酸化染料) 多くのカラー剤に含まれる成分で、アレルギー反応を起こしやすいのが特徴。頭皮の炎症や湿疹を引き起こし、重症化すると腎臓障害などを引き起こす可能性も報告されています。
アレルギー性接触皮膚炎になると、頭皮のかゆみや赤み、腫れ、ブツブツができるだけでなく、症状が重くなると顔全体が腫れたり、水ぶくれができたりすることも。さらに重症化すると、アナフィラキシーショックによって呼吸困難や血圧低下を引き起こす危険性もあります。
髪へのダメージも深刻
カラー剤は髪にも大きなダメージを与えます。特にブリーチを使った明るい色にする場合は要注意です。
繰り返しカラーをすると、髪が切れやすくなったり、ゴワゴワした手触りになったり、最悪の場合は髪が溶けてしまうこともあります。実際に「触るだけで髪が切れる」「髪がめちゃくちゃ痛んだ」という声も少なくありません。
美容師さんたちの間でも、子どもへのヘアカラーは慎重になるべきだという意見が主流です。日本皮膚科学会も「低年齢での毛染めはアレルギー発症の危険性がある」と警鐘を鳴らしていますし、皮膚科医も「思春期前半(小学校高学年から中学生)は染毛を避けるべき」と指摘しています。
学校の校則と髪染め、法律的にはどうなの?
校則で髪染めを禁止するのは合法?
実は、校則について定めた法律は日本にはありません。しかし、裁判所の判例では「学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的範囲内において校則を制定できる」とされています。
過去の判例を見ると、茶髪禁止の校則は「社会通念上合理的と認められる範囲」として合法とされることが多いです。ただし、生まれつきの髪色を黒く染めるよう強要するのは人権侵害にあたる可能性があります。
校則が緩い学校と厳しい学校の違い
最近では、校則の見直しを進める学校が増えています。岐阜県の県立岐山高校では、2023年に「髪の色や化粧に関する校則」を試験的に廃止しました。その後のアンケートでは、髪を染めたりメイクをした生徒は全体の4分の1ほどいましたが、学習時間に大きな違いは見られず、「風紀が乱れた」と回答したのは約1割だけでした。
一方で、多くの中学校では依然として「染色・脱色禁止」という校則が存在します。学校によって対応はさまざまで、通っている学校の校則をしっかり確認することが大切です。
校則違反した場合のペナルティは?
公立中学校の場合、高校のように停学や退学といった処分はできません。ただし、以下のような指導が行われることがあります。
- 担任や生活指導の教員からの個別指導
- 保護者への連絡と面談
- 黒染めの指示
- 場合によっては内申書への影響
校則違反を繰り返すと、内申書にマイナスの影響が出る可能性もあるため、高校受験を控えている場合は特に注意が必要です。
親として子どもの「髪を染めたい」にどう向き合う?
まずは「なぜ染めたいのか」を聞いてみよう
子どもが「髪を染めたい」と言ってきたとき、頭ごなしに「ダメ」と言うのではなく、まずは理由を聞いてみることが大切です。
単純におしゃれに興味があるのか、友達の影響なのか、それとも何か別の悩みがあるのか。理由によって対応も変わってきます。もし友達関係や家庭の悩みから来ている場合は、その根本的な問題に向き合う必要があるかもしれません。
メリットとデメリットを一緒に考える
髪を染めることのメリットとデメリットを、子どもと一緒に整理してみましょう。
メリット
- おしゃれを楽しめる
- 自分らしさを表現できる
- 気分転換になる
- 周りの友達と同じようにできる
デメリット
- 頭皮や髪への健康リスク
- 学校で注意される可能性
- 周りからの印象が変わるかも
- 維持費がかかる(プリンになる)
- 受験や就職活動で不利になる可能性
これらを踏まえて、本当に今染める必要があるのか、もう少し待ってからの方がいいのか、一緒に考えてみるといいでしょう。
妥協案を提案してみる
どうしても染めたいという場合は、以下のような妥協案を提案してみるのも一つの方法です。
一時的なカラーを試す ヘアマニキュアやカラートリートメントなど、洗えば落ちるタイプのカラー剤なら、ダメージも少なく済みます。
夏休みだけOK 長期休暇中だけ染めて、学校が始まる前に戻すというルールを決める。
毛先や内側だけ 全体を染めるのではなく、インナーカラーやグラデーションなど、部分的なカラーにする。
高校生になったら 「高校生になって校則で許可されていればOK」という約束をする。
美容院で染める場合の注意点
もし髪を染めることを許可する場合は、必ず信頼できる美容院で染めてもらいましょう。多くの美容院では、未成年者がカラーをする場合は親の同伴や承諾を必要としています。
美容師さんは髪質や頭皮の状態を見て、適切なカラー剤や染め方を提案してくれます。セルフカラーはムラになりやすく、頭皮に薬剤がたくさん付着してしまうリスクも高いため、避けた方が無難です。
校則がある学校で髪を染めた場合はどうなる?
先生にバレたときの対応
もし校則で禁止されているのに髪を染めてバレた場合、以下のような流れで指導されることが多いです。
- 担任の先生から事情聴取
- 保護者への連絡
- 黒染めの指示
- 反省文の提出を求められることも
大切なのは、先生に対して誠実な態度で接すること。反抗的な態度を取ると、余計に事態が悪化してしまいます。
言い訳は通用する?
「プールで日焼けして色が変わった」「シャンプーで色が抜けた」などの言い訳は、先生には通用しないことがほとんど。嘘をつくよりも、正直に「染めました」と認めた方が、先生からの印象も良くなります。
もし成績が良くて普段の態度も真面目な生徒であれば、厳しく叱られることは少ないかもしれません。ただし、それでも校則違反は校則違反。今後は染めないという約束をすることになるでしょう。
中学生の髪染め、実際に経験した人の声
私も中学生の頃、友達が髪を染めていて羨ましく思ったことがあります。当時通っていた学校は髪染め禁止だったので実際には染めませんでしたが、もし染めていたら今の髪の状態はどうなっていたんだろうと考えることがあります。
友人の中には、中学時代に何度も髪を染めて、高校生になる頃には髪がボロボロになってしまった子もいました。一時的なおしゃれのために、長期的なダメージを受けてしまうのは本当にもったいないことだと思います。
また別の友人は、親に相談してヘアマニキュアを使うことで妥協点を見つけました。洗えば落ちるタイプなので、週末だけ楽しんで月曜日には黒髪に戻すという方法です。こうした工夫で、髪へのダメージを最小限に抑えながらおしゃれを楽しむこともできますね。
髪染め以外でおしゃれを楽しむ方法
髪を染めなくても、中学生がおしゃれを楽しむ方法はたくさんあります。
ヘアアレンジを極める 編み込みやくるりんぱ、お団子など、ヘアアレンジの技術を磨けば、黒髪でも印象を変えられます。YouTubeやInstagramには簡単にできるアレンジ動画がたくさんあるので、参考にしてみてください。
ヘアアクセサリーを活用 シンプルなヘアゴムやピン、カチューシャなど、校則で許可されている範囲でヘアアクセサリーを楽しむのもいいですね。
ファッションで個性を出す 制服のアレンジや、私服の日のコーディネートで個性を表現するのも一つの方法です。
メイクやネイルの勉強 将来のために、今はメイクやネイルの知識を蓄えておくのもいいでしょう。休日に練習してみるのも楽しいですよ。
地毛が茶髪とか言ってるけど染めたんじゃ無いの?中学生の女
— 姫咲 ゆり (@_hime_s_) October 1, 2025
海外では中学生の髪染めはどう見られている?
日本では中学生の髪染めに対して厳しい意見も多いですが、海外ではどうなのでしょうか?
実は国や地域によって考え方はさまざまです。アメリカやヨーロッパの一部の国では、髪色は個人の自由として尊重される傾向が強く、学校でも特に制限がないことが多いです。
ただし、海外でも「勉強をきちんとしていれば問題ない」という考えは共通しています。成績が悪かったり素行に問題があったりする場合は、髪染めについても注意されることがあるようです。
日本でも徐々に個人の自由を尊重する方向に変わってきていますが、まだまだ保守的な考え方が根強く残っているのが現状です。
よくある質問
Q1:中学生で髪を染めても法律違反にはならない?
法律で中学生の髪染めを禁止する規定はありません。ただし、学校の校則で禁止されている場合は、校則に従う必要があります。校則は法律ではありませんが、学校が教育目的で定めたルールとして一定の拘束力を持ちます。
また、美容院で染める場合、多くのお店では未成年者には親の同意を必要としています。これは健康リスクを考慮してのことなので、親に内緒で染めることは避けましょう。
Q2:一度染めたら元に戻せない?
カラー剤で染めた髪は、完全に元の色に戻すことは難しいです。黒染めをしても、時間が経つと色が抜けて茶色っぽくなることがあります。
また、黒染めを繰り返すと髪へのダメージが蓄積されます。「染めて後悔したから戻す」を繰り返すのは、髪にとって最悪のパターンです。
本当に染めたいのか、染めたあとのことまで考えているか、よく考えてから決めることが大切です。
Q3:カラートリートメントやヘアマニキュアなら安全?
通常のカラー剤と比べると、カラートリートメントやヘアマニキュアは髪や頭皮へのダメージが少ないとされています。これらは髪の表面に色をつけるだけで、髪の内部構造を変えないからです。
ただし、完全に無害というわけではありません。肌が弱い人はかぶれることもあるので、使用前にパッチテストを行うことをおすすめします。
また、色持ちが悪く、シャンプーのたびに少しずつ色が落ちていくため、頻繁に染め直す必要があります。
Q4:友達はみんな染めてるのにうちだけダメって言われた。どうすればいい?
「みんなやってる」は親を説得する理由にはなりません。大切なのは、あなた自身がなぜ染めたいのか、その理由を親にしっかり伝えることです。
また、親が心配しているのは、あなたの健康や将来のことです。その心配を理解した上で、「こういう対策をするから大丈夫」と具体的に提案してみましょう。
例えば「美容院で染める」「定期的にトリートメントをする」「成績を維持する」など、親が安心できる条件を提示するのも一つの方法です。
それでもダメと言われたら、今は我慢して、高校生になったら改めて相談してみるという選択肢もあります。
Q5:髪を染めると将来ハゲるって本当?
カラー剤そのものが直接的に脱毛を引き起こすことはないとされています。ただし、頻繁にカラーを繰り返すと、頭皮環境が悪化したり髪がダメージを受けたりすることで、間接的に薄毛につながる可能性はあります。
特に中学生のうちから繰り返しカラーをすると、大人になってから頭皮トラブルが出やすくなるという指摘もあります。
「将来ハゲる」というのは極端な表現ですが、髪や頭皮への負担が大きいことは事実です。染めるなら、できるだけダメージを抑える方法を選び、頻度も控えめにすることが大切です。
Q6:学校の校則で禁止されているけど、バレずに染める方法はある?
正直に言うと、バレずに染める方法を探すよりも、校則に従うか、校則の見直しを学校に提案する方が建設的です。
隠れて染めてバレた場合、先生からの信頼を失うだけでなく、内申書に影響が出る可能性もあります。特に受験を控えている場合は、リスクが大きすぎます。
どうしても染めたいなら、校則が緩い高校を選んで進学するという選択肢もあります。今は我慢して、将来堂々とおしゃれを楽しめる環境を選ぶのも一つの方法です。
「ヘアカラー」の人気商品をレビュー件数順に楽天でチェック!まとめ:中学生の髪染めは慎重な判断を
中学生の髪染めについて、さまざまな角度から見てきました。最後に大切なポイントをまとめます。
健康面のリスクを理解しよう 中学生の頭皮や髪はまだ発達途中で、カラー剤による影響を受けやすい状態です。アレルギーや髪のダメージなど、健康リスクがあることを理解した上で判断しましょう。
校則の確認を忘れずに 自分の学校の校則をしっかり確認し、禁止されている場合はルールに従うことが基本です。ただし、不合理な校則については、適切な方法で見直しを提案することもできます。
親子でよく話し合おう 「染めたい」という気持ちの背景には何があるのか、親子でじっくり話し合うことが大切です。頭ごなしに禁止するのではなく、メリット・デメリットを一緒に考えて、納得できる答えを見つけましょう。
代替案も検討してみる 髪を染める以外にも、おしゃれを楽しむ方法はたくさんあります。ヘアアレンジやヘアアクセサリー、ファッションなど、他の方法も試してみてはいかがでしょうか。
将来のことも考えて 一時的なおしゃれのために、長期的な健康リスクを負うことがないよう、慎重に判断しましょう。「今じゃなくてもいいかも」と思えるなら、もう少し待つのも賢い選択です。
中学生という時期は、自分らしさを探し、表現したいという気持ちが強くなる大切な時期です。その気持ちは尊重されるべきですが、同時に健康や将来のことも考えて、バランスの取れた判断をすることが重要です。
髪を染めるかどうかは、結局のところ個人の選択です。でも、その選択をする前に、今回お伝えしたような情報をしっかり理解して、後悔のない決断をしてくださいね。