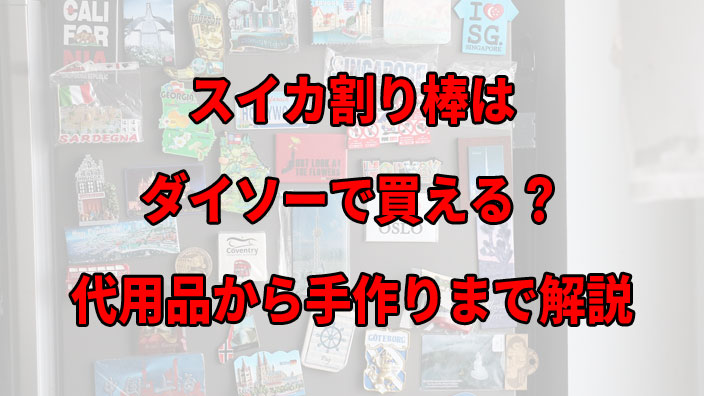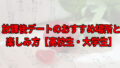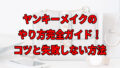夏のイベントといえばスイカ割りですよね。家族や友達とワイワイ楽しめる最高の遊びなんですが、「スイカ割りの棒ってどこで買えばいいの?」と困っている方も多いのではないでしょうか。専用の棒をわざわざ買うのもちょっと…と思いますよね。
実は、ダイソーをはじめとした100円ショップには、スイカ割りに使える便利なアイテムがたくさんあるんです。この記事では、ダイソーで買える代用品から、家にあるもので簡単に手作りする方法、さらに安全に楽しむためのポイントまで、スイカ割り棒に関するすべてを詳しく解説していきます。
ダイソーでスイカ割り棒は売ってるの?
結論からお伝えすると、ダイソーには「スイカ割り棒」という名前の商品は販売されていません。セリアやキャンドゥなど他の100円ショップでも、専用の棒は見つかりませんでした。
でも心配しないでください。ダイソーには、スイカ割りに使える代用品がいろいろあるんです。工夫次第で十分にスイカ割りを楽しめますよ。
ダイソーで買えるスイカ割り棒の代用品
ダイソーで手に入る、スイカ割りに使えるアイテムをご紹介します。それぞれのメリット・デメリットも一緒に見ていきましょう。
木製めん棒
マッサージ用にダイソーで木製のめん棒買ったんだけど、私の肌には合わなくて痒くなってしまって。ヤスリで表面滑らかにすればいいんだけど、めんどかったのでプラスチック製のめん棒買ったら硬さも重さも使いやすそうな予感… pic.twitter.com/jDo8ySRLLZ
— レイ* (@HeAetique) July 27, 2017
ダイソーのキッチン用品コーナーで販売されている木製めん棒は、スイカ割り棒の代用品として人気です。価格は110円で、長さは約32〜33cmほどです。
木製なので適度な重さがあり、大人も子どもも扱いやすいのが魅力です。本来は料理用なので、スイカ割りが終わったらクッキーやパン作りにも使えて一石二鳥ですね。
ただし、長さが少し短めなので、子ども用としては問題ありませんが、大人が使う場合は少し物足りないかもしれません。また、木製なので重量感があるため、小さい子どもに持たせる場合は振り下ろしたときに当たるとケガの恐れがあります。周りの安全確認をしっかり行ってから使いましょう。
園芸用支柱
ダイソーに連結できる園芸用支柱が売ってた。
— ついすら (@tuisura21) November 3, 2023
長柄武器を作る時に便利そうだな pic.twitter.com/jjBwchG3jE
ダイソーの園芸コーナーで販売されている支柱も、スイカ割り棒として使えます。長さが調整しやすく、軽量なのが特徴です。
単品だと強度が足りない場合があるので、数本を束ねてガムテープやビニールテープでしっかり固定すると良いでしょう。長さも十分あるので、大人でも使いやすいです。
突っ張り棒
ダイソーで突っ張り棒買って吊り下げプランターにぬい入れてみた
— アユト (@Ayuto_0625) January 24, 2025
明日S字フック買って大きいぬいも入るプランターも買ってみる pic.twitter.com/UblyfSU53p
意外かもしれませんが、突っ張り棒もスイカ割りに使える優秀なアイテムです。最大のメリットは、長さを自由に調整できること。子どもから大人まで、使う人に合わせて長さを変えられるのは本当に便利です。
軽量で扱いやすく、まっすぐな構造をしているため、スイカを狙いやすいのも良いポイントです。ダイソーでは様々な長さの突っ張り棒が売られているので、用途に合わせて選んでみてください。
子ども用おもちゃバット
木製バット(笑)
— 天音⚜️11/24仙コミ予定 (@redsky108) April 22, 2018
ダイソーのおもちゃのバットに塗料(アイボリーとモカチャ)
塗装時間5分 pic.twitter.com/BUJbN04Um5
ダイソーのおもちゃコーナーには、プラスチック製の軽いバットが販売されています。これも子ども向けのスイカ割り棒として最適です。
カラフルなデザインのものが多いので、イベントの雰囲気も盛り上がります。プラスチック製なので、万が一人に当たっても痛くなりにくく、安全性が高いのも嬉しいですね。
家にあるもので代用できるスイカ割り棒
ダイソーに行かなくても、家にあるもので十分にスイカ割りが楽しめます。急にスイカ割りをすることになった時にも使えるアイデアをご紹介します。
新聞紙で手作り
我が末っ子も一人前に新聞紙を丸めた棒でスイカを割るようになりました((◆*´凵`w)ヾ
— c8h15n→ダイエット中 (@coniceine_0917) August 22, 2017
家の庭ではしゃぎながら楽しむスイカ割りはやっぱり楽しいっ
(≧∇≦) pic.twitter.com/1HaTSo4vEJ
新聞紙を使えば、費用ゼロで立派なスイカ割り棒が作れます。作り方も簡単で、新聞紙を何枚も重ねてしっかり丸めていくだけです。
まず、新聞紙を1枚広げて、端からきつく巻いていきます。これを芯にして、さらに新聞紙を巻き重ねていくことで強度を上げます。長さは80〜120cm程度を目安に調整しましょう。
芯ができたら、ガムテープでしっかり巻いて固定します。持ち手の部分にビニールテープを巻くと、滑りにくくなって握りやすくなりますよ。食品に触れる部分は、食品用ラップを巻いておくと衛生的です。
コツは、芯を作る段階からきつく固く巻くこと。隙間があると、スイカに数回当てただけでぐにゃっとなってしまうので注意してくださいね。
ラップの芯
ラップやアルミホイルの芯も、意外と丈夫でスイカ割りに使えます。特に大きいサイズのラップの芯なら、長さも十分です。
複数の芯を重ねて束ねることで、さらに強度を上げることができます。持ち手の部分にテープを巻いて滑り止めを作れば、より使いやすくなります。
ほうきの柄
家にあるほうきの柄部分も、スイカ割りの棒として使えます。長さがちょうど良く、しっかりした持ち手があるため、大人が使う場合にも安定感があります。
ただし、使用する際は必ず先端にタオルや布を巻いて、クッション性を持たせてください。硬い素材がそのまま当たると、スイカが割れすぎてしまったり、思わぬケガにつながる可能性もあります。
使用前にしっかり洗浄・消毒することも忘れずに。見た目を可愛くしたいなら、リボンや色テープで装飾するのも良いですね。
物干し竿
ステンレス製の物干し竿も、スイカ割り棒として活用できます。長さが調整できるタイプなら、子どもの身長に合わせて使えるので便利です。
細さは直径3cm程度で持ちやすく、ステンレス製なので適度な重さもあります。ただし、金属製なので子どもがふざけて振り回すと危険です。使用する際は、必ず大人が近くで見守るようにしてください。
ダイソー以外で買えるスイカ割り棒
もう少し本格的なスイカ割り棒が欲しい方には、他のお店での購入もおすすめです。
ホームセンターのめん棒
ホームセンターには、80cm前後の長さの本格的なめん棒が販売されています。うどんやそば打ちに使うめん棒は、スイカ割りにぴったりの長さと重さなんです。
食品に触れることを前提に作られているので衛生面も安心です。心配な場合は、食品用ラップを巻いて使いましょう。持ち手にビニールテープを巻くと、滑りにくくなってさらに使いやすくなります。
スイカ割りだけでなく、本格的な麺作りにも挑戦したいと考えている方には特におすすめです。
野球バット
強度、重さ、握りやすさ、破壊力のすべてを兼ね備えているのが野球のバットです。スイカを確実に割りたいなら、これ以上のアイテムはないかもしれません。
ただし、そのまま使うのは不衛生なので、必ず消毒するか食品用ラップを巻いてください。また、力に自信がある方がフルパワーで振り下ろすと、スイカがかなりグチャグチャになってしまうので、力加減には注意が必要です。
ホームセンターの角材
DIYが好きな方は、ホームセンターで角材を購入してカスタマイズするのも良いでしょう。80cm程度にカットしてもらい、子ども用なら直径3cm、大人用なら5cmが握りやすいサイズです。
購入後は、サンドペーパーで表面を滑らかに磨いて、ささくれで手を傷つけないようにします。持ち手にビニールテープを巻けば、滑り止め効果も得られます。
ただし、軽すぎる材料は強度が低いので、適度な重さのある木材を選ぶことが大切です。
公式スイカ割り棒セット
実は、JAが公式に認定したスイカ割り専用棒セットというものが存在します。このセットは、握りやすさやスイカの割りやすさを徹底的に研究して作られた本格的な商品です。
棒を振り下ろしたときに最大限のパワーがスイカに伝わるように設計されているので、子どもや力の弱い方でもスイカを割ることができます。公式ルールブックや目隠し用の手ぬぐいもセットになっているので、これひとつで本格的なスイカ割り大会が開催できます。
毎年恒例でスイカ割りを楽しんでいるご家庭なら、専用セットを購入しても損はありませんよ。
スイカ割り棒の選び方のポイント
スイカ割りを成功させるためには、適切な棒を選ぶことが大切です。選び方のポイントを詳しく見ていきましょう。
長さは80〜120cmが目安
スイカ割りの公式ルールでは、棒の長さは120cm以内と定められています。家族や友人と楽しむなら、80〜120cm程度の長さがおすすめです。
短すぎると距離感がつかみにくく、スイカに届かないことも。逆に長すぎるとバランスを崩しやすく、周りの人に当たる危険性も高くなります。
大人が使う場合は100〜120cm、子どもが使う場合は70〜90cmが扱いやすいでしょう。参加者の年齢や身長に合わせて、複数の長さの棒を用意するのも良い方法です。
重さは500〜800g程度が理想
スイカを割るには、ある程度の重さが必要です。剣道の竹刀は長さ120cmで重量510g以上と規定されていますが、これを参考にすると、500〜800g程度の重さがあると扱いやすくスイカも割りやすいでしょう。
軽すぎるとスイカに当たっても割れにくく、重すぎると振り下ろすのが大変で、子どもには扱いにくくなります。特に小さな子どもが参加する場合は、軽めの棒を選んであげると良いですね。
素材は木製やプラスチック製がおすすめ
棒の素材も重要なポイントです。木製の棒は適度な重さと強度があり、スイカを割りやすいのが特徴です。しっかりした作りなので、命中すればきれいにスイカが割れます。
プラスチック製は軽量で扱いやすく、初心者や子どもにも向いています。万が一人に当たってもケガをしにくいという安全面でのメリットも大きいです。
スポンジ素材の棒は、当たっても痛くない設計で、小さな子どもが使う場合に最も安全です。ただし、スイカを割る威力はやや弱めなので、小玉スイカと組み合わせるのがおすすめです。
金属製の棒は重すぎて扱いにくく、当たったときの衝撃が強すぎるため、家族で楽しむスイカ割りには向きません。
持ちやすさをチェック
手にしっかりフィットする太さで、滑りにくい表面のものを選びましょう。振りかぶったときに安定することが大切です。
また、尖った部分がなく、丸みのあるデザインを選ぶのも安全面で重要です。特に子どもが使う場合は、先端を柔らかい素材でカバーするか、先端を丸めた棒を使うと良いでしょう。
恐いスイカ割り🍉 pic.twitter.com/ZnDHPs3ZEp
— りんだ💎 (@adnilst51tko921) November 1, 2025
スイカ割りを安全に楽しむための注意点
楽しいスイカ割りですが、安全対策を怠ると思わぬ事故につながる可能性があります。
折れやすい素材は避ける
細すぎる木の棒や古い竹など、折れやすい素材は絶対に避けてください。棒を振る際には勢いがつくため、折れた瞬間に破片が飛ぶ可能性があり、非常に危険です。
事前に実際に振ってみて、手の感覚や重さのバランスを確認することが安全につながります。少しでも不安を感じたら、その棒は使わないようにしましょう。
周囲との距離をしっかり確保
スイカ割りでは振り下ろす動作があるため、周囲との距離をしっかり確保することが最も重要です。振る人の周りには少なくとも3メートル以上の空間を確保しましょう。
子どもは夢中になると加減ができないこともあるので、周囲の人との距離や立ち位置を明確に伝えておくことが大切です。目隠しをしている間は、必ず大人が近くで見守り、危険がないかチェックしてください。
広くて安全な場所を選ぶ
スイカ割りを行う場所は、芝生の公園やビーチなど、広くて柔らかい地面がある場所が理想的です。狭い場所や硬いコンクリートの上では行わないようにしましょう。
スイカを固定するためのネットや台も用意しておくと、スイカが転がらず安全です。周囲に障害物がないか、人がいないか、必ず確認してから実施してください。
目隠しは視界を適度に遮るものを
目隠しは安全な素材で、視界を完全にふさぎすぎないものを使いましょう。完全に何も見えない状態だと、転倒の危険性が高まります。
柔らかい布製のバンダナや手ぬぐいがおすすめです。ダイソーでもアイマスクやバンダナが手軽に揃います。
棒の素材を事前にチェック
使用する前に、棒に鋭利な部分やささくれがないか必ずチェックしてください。万が一見つかった場合は、サンドペーパーで滑らかにするか、テープで保護しましょう。
衛生面にも配慮を
スイカは食べ物なので、衛生面への配慮も忘れずに。棒の先端に食品用ラップを巻いたり、使用前に消毒したりすることをおすすめします。
割ったスイカはすぐに食べられるよう、清潔なトレイや包丁、まな板も準備しておきましょう。ウェットティッシュや水も用意しておくと便利です。
スイカ割りをもっと盛り上げる工夫
基本的な準備ができたら、さらに楽しくする工夫も取り入れてみましょう。
棒を装飾してみる
棒にカラフルなビニールテープやマスキングテープを巻いて装飾すると、見た目が華やかになります。子どもたちが喜ぶキャラクターのシールを貼るのも良いですね。
風船やクッション素材を先端に取り付けることで、安全性と楽しさを両立できます。動物やキャラクターの絵を貼れば、子どもたちのテンションもさらにアップしますよ。
目隠しを工夫する
ダイソーで売っているカラフルなバンダナを使えば、イベント感が演出できます。デザインも豊富で、写真映えもバッチリです。
掛け声や音楽で盛り上げる
「右!右!」「もうちょっと前!」といった掛け声で、みんなで盛り上がりましょう。応援係を決めて、大きな声で応援するのも楽しいですよ。
音楽をかけたり、BGMを流したりして、会場の一体感を高めるのもおすすめです。夏らしい明るい曲を選ぶと、雰囲気がさらに良くなります。
ルールをアレンジする
公式ルールに縛られず、参加者に合わせてルールをアレンジするのも楽しみ方のひとつです。
小さな子どもには回転数を減らしたり、目隠しを軽くしたりして、難易度を下げてあげましょう。逆に大人だけで楽しむなら、回転数を増やしたり、距離を遠くしたりして難しくするのも盛り上がります。
チーム対抗戦にして、制限時間内に割れたチームから順位をつけるのも面白いですね。
よくある質問
Q1. スイカ割り棒は絶対に専用のものでないとダメですか?
いいえ、専用の棒でなくても全く問題ありません。ダイソーで買える代用品や、家にあるもので十分に楽しめます。大切なのは、安全性と適度な強度があることです。
新聞紙を丸めて作った手作りの棒でも、しっかり固く巻けばスイカを割ることができます。むしろ、身近なもので工夫する過程も楽しみのひとつですよ。
Q2. 子どもと大人で棒を分けたほうがいいですか?
できれば分けることをおすすめします。子どもには軽くて短めの棒、大人にはしっかりした長めの棒を用意すると、それぞれが楽しみやすくなります。
子ども用にはスポンジバットやプラスチック製のおもちゃバット、大人用には木製めん棒や野球バットなど、参加者に合わせて選んであげましょう。
Q3. スイカ割りの棒の長さに決まりはありますか?
公式ルールでは「直径5cm以内、長さ120cm以内」と定められています。ただし、家族や友人同士で楽しむ場合は、そこまで厳密にする必要はありません。
安全に配慮しながら、使う人が扱いやすい長さを選ぶのが一番です。一般的には80〜120cm程度が使いやすいでしょう。
Q4. ダイソーのめん棒でも本当にスイカは割れますか?
はい、割れます。ダイソーの木製めん棒は適度な重さと強度があるので、しっかり振り下ろせばスイカを割ることができます。
ただし、長さが短めなので、大きなスイカを割るには少し苦労するかもしれません。小玉スイカや子ども用として使う分には十分です。
Q5. 棒を振ったときに折れたりしませんか?
適切な素材と強度の棒を選べば、折れる心配はほとんどありません。細すぎる木の棒や古い竹など、明らかに強度が足りないものは避けましょう。
新聞紙で作る場合も、芯をしっかり固く巻いて、さらに新聞紙を重ねて強度を上げることで、折れにくい棒が作れます。
Q6. スイカ割りの後、棒は捨てるべきですか?
新聞紙で作った使い捨ての棒以外は、次回のために保管しておくのがおすすめです。ダイソーのめん棒や野球バットなら、本来の用途でも使えますよね。
木製の棒は使用後にしっかり洗って乾燥させれば、何度でも使えます。専用の棒として保管しておけば、来年のスイカ割りでもすぐに使えて便利です。
Q7. 室内でスイカ割りをする場合の注意点は?
室内でスイカ割りをする場合は、特に安全面に気をつけましょう。広いスペースを確保し、周囲に壊れやすいものがないか確認してください。
床が硬い場合は、ブルーシートやマットを敷くことをおすすめします。また、棒は軽めで柔らかい素材のものを選び、力加減にも注意が必要です。
Q8. 一番おすすめのダイソーの代用品は何ですか?
子ども中心のイベントなら、スポンジバットやプラスチック製のおもちゃバットが安全でおすすめです。大人も参加するなら、木製めん棒や突っ張り棒が良いでしょう。
突っ張り棒は長さ調整ができるので、子どもから大人まで使える点で特に便利です。予算に余裕があれば、複数種類用意して使い分けるのが理想的ですね。
「スイカ割り」の人気商品をレビュー件数順に楽天でチェック!まとめ
スイカ割り棒は、ダイソーなどの100円ショップで代用品を手軽に入手できます。木製めん棒、園芸用支柱、突っ張り棒、おもちゃバットなど、用途に合わせて選べる商品が揃っています。
また、新聞紙、ラップの芯、ほうきの柄、物干し竿など、家にあるものでも十分に代用可能です。特に新聞紙を使った手作り棒は、費用もかからず急なイベントにも対応できて便利です。
棒選びのポイントは、長さ80〜120cm、重さ500〜800g程度、木製かプラスチック製が理想的です。安全性を最優先に考え、参加者の年齢や力に合わせて選びましょう。
より本格的に楽しみたい方は、ホームセンターのめん棒、野球バット、角材、公式スイカ割り棒セットなどもおすすめです。それぞれの特徴を理解して、用途に合わせて選ぶと良いでしょう。
安全に楽しむためには、折れやすい素材を避ける、周囲との距離を確保する、広い場所で行う、目隠しの選び方に気をつけるなどの注意が必要です。特に子どもが参加する場合は、必ず大人が近くで見守り、安全確認を徹底してください。
この夏は、ダイソーのアイテムや家にあるもので「マイ・スイカ割り棒」を用意して、家族や友人と素敵な思い出を作ってくださいね。