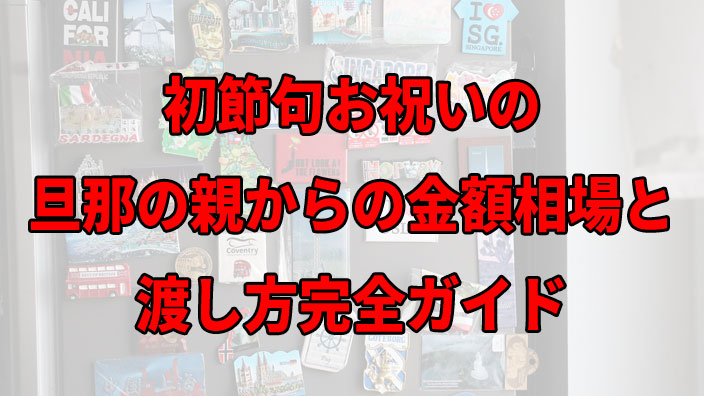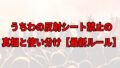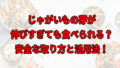子どもの初節句が近づいてくると、旦那の親からいくらくらいお祝いをもらうのが普通なのか、気になりますよね。初めての経験だと特に、金額のことや役割分担について不安に感じることも多いはずです。この記事では、旦那側のご両親からの初節句のお祝い金額の相場から、両家の役割分担、マナーまで詳しく解説していきます。
初節句とは?基本を押さえておこう
初節句は、赤ちゃんが生まれて初めて迎える節句のことです。女の子なら3月3日の桃の節句、男の子なら5月5日の端午の節句がそれにあたります。
ただし、2月や3月生まれの女の子、4月や5月生まれの男の子の場合は、生まれてすぐになってしまうので、1歳になった翌年にお祝いすることも多いんですよ。無理せず赤ちゃんの成長に合わせて決めて大丈夫です。
初節句では、女の子は雛人形、男の子は五月人形や兜などの節句飾りを飾り、家族や親戚を招いて食事会を開くのが一般的です。子どもの健やかな成長と厄除けを願う大切な行事なんですね。
旦那の親からのお祝い金額の相場は?
父方の祖父母の相場
旦那の親、つまり父方の祖父母からのお祝い金額の相場は、一般的に5万円から20万円程度とされています。
ただし、これはあくまでも目安です。地域によっても違いますし、それぞれの家庭の経済状況や考え方によっても大きく変わってきます。
実際に私の周りでも、10万円のお祝いをもらったという友人もいれば、節句飾りの購入費用として両家で折半したという人もいました。本当にケースバイケースなんですよね。
母方の祖父母との違い
昔からの風習では、母方の祖父母が節句飾りを贈り、父方の祖父母はお祝いの準備をするという役割分担がありました。そのため、母方の祖父母の相場は10万円から30万円程度と、やや高めに設定されていることが多いです。
これは、昔は女性が父方の家に嫁入りするのが一般的だったため、母方の実家が節句飾りという形で娘と孫を応援する意味があったんです。
でも、現代では核家族化が進んで住宅事情も変わってきましたから、こういった役割分担は厳格にされなくなっています。両家で話し合って柔軟に決めることが増えていますよ。
内孫と外孫で金額に差がある?
「内孫」「外孫」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
内孫とは、息子の子ども(つまり旦那側から見た孫)のことで、外孫とは娘の子ども(奥さん側から見た孫)のことを指します。
昔の風習では、内孫には節句飾りを贈らなくても良いとされていたため、お祝い金が3万円から20万円と幅がありました。一方、外孫には節句飾りを贈る慣習があったため、5万円から20万円程度と少し高めの設定でした。
ただし、これも地域や家庭によって大きく異なりますし、現代ではこうした区別をしない家庭も増えています。きょうだい間で差が出ないよう、一律のお祝い金を渡すケースも多いんですよ。
義母、うちの子ども1人だと思ってんのかな🫤明日の初節句のお祝いにおもちゃ買ってもらったんだけど、どれもこれも1つずつ。手持ちの小さいのも1つ。金額見るのって失礼を承知ですが、私の母と叔父から10万ずつ頂いてて、義母は1万未満。気持ちがこの程度なら私もそれに習います。
— みーや☺︎ ︎双子BOYS🍧🎐1y(修正1y) (@miyass0687) May 4, 2025
旦那の親からお祝いがない場合もある?
「旦那の親からお祝いがこないけど、これって普通なの?」と不安に思う人もいるかもしれません。
実は、これにはいくつかの理由が考えられます。
まず、先ほど説明した昔の役割分担の考え方が残っている地域では、父方の祖父母は節句飾りではなく、食事会の準備や当日のおもてなしを担当するという認識の場合があります。
また、両家で事前に「節句飾りの購入費用を折半しましょう」と相談していて、旦那の親がすでに半分の費用を負担している可能性もあります。
もし不安な場合は、旦那さんを通じて確認してもらうのが一番です。直接義両親に聞くのは気まずいかもしれませんが、旦那さんなら気軽に確認できますよね。
両家の役割分担はどう決める?
昔の役割分担
伝統的には、こんな役割分担がありました。
母方の祖父母:節句飾り(雛人形や五月人形)を購入して贈る 父方の祖父母:初節句当日の食事会の準備やおもてなしをする
でも、これはあくまで昔の話。今は必ずしもこの通りにする必要はありません。
現代の柔軟な決め方
最近では、こんな方法で両家が協力しているケースが多いですよ。
節句飾りは若い夫婦が選んで、購入費用を両家で折半する方法です。これなら、好みの飾りを選べますし、両家の負担も公平になりますね。
私の友人も、この方法を取っていました。インテリアに合う小ぶりな雛人形を夫婦で選んで、費用は両家で半分ずつ負担してもらったそうです。「自分たちで選べたから満足だし、両家にも気を遣わせずに済んだ」と言っていました。
母方の祖父母が節句飾りを贈り、父方の祖父母はお祝い金を渡すという方法もあります。
節句飾りの購入はせず、両家それぞれがお祝い金を包むという選択肢もあります。住宅事情で大きな飾りを置けない場合などに便利ですね。
大切なのは、両家で事前に相談して、お互いが納得できる方法を見つけることです。どちらか一方に負担が偏ると、後々の関係性がギクシャクしてしまう可能性もありますから。
お祝い金を渡すタイミングはいつ?
お祝い金を渡すタイミングも気になるポイントですよね。
一般的には、初節句の1週間から1か月前までに渡すのがマナーとされています。これは、節句飾りを購入したり、食事会の準備をしたりする時間的な余裕を持たせるためです。
節句飾りの購入費用として渡す場合は、もう少し早めに渡すことも多いです。特に雛人形は1月頃から、五月人形は3月頃から店頭に並び始めるので、それに合わせて渡すと親切ですね。
遠方に住んでいて直接会えない場合は、現金書留で送ることもできます。その際は、一言メッセージを添えると気持ちが伝わりますよ。
お祝い金の渡し方とマナー
のし袋の選び方
お祝い金を包む際は、紅白の花結び(蝶結び)の水引がついた祝儀袋を使います。
花結びは何度でも結び直せることから、何度あっても良いお祝い事に使われます。初節句はまさにそれに当たりますね。
表書きには「初節句御祝」や「祝初節句」と書きます。下段には、贈る人の名前を書きましょう。祖父母の連名でも、苗字だけでも構いません。
中袋には、金額と住所、氏名を記入します。住所は、お返しを贈る時に確認することもあるので、省略せずに書いておくと親切です。
書き方のポイント
筆や筆ペンを使って、太く濃く丁寧に書くのがマナーです。
最近はボールペンで書く人もいますが、お祝い事ですから、できれば筆ペンを使いたいものです。100円ショップでも購入できるので、用意しておくと良いですよ。
金額は、「金 壱萬円」「金 伍萬円」など、旧字体(大字)で書くのが正式です。これは、改ざんを防ぐためなんですね。
節句飾りを贈る場合の注意点
お祝い金ではなく、節句飾りそのものを贈りたいという祖父母も多いですよね。
その場合、絶対に守ってほしいのが「必ず赤ちゃんの両親に相談する」ということです。
勝手に選んで贈ってしまうと、こんなトラブルが起こる可能性があります。
すでに別の人から贈られることになっていた、マンションやアパートで大きな飾りを置くスペースがない、インテリアの雰囲気に合わない、両親が別のデザインを希望していた。
私の知り合いで、義両親が大きな七段飾りを贈ってくれたけど、アパートに置く場所がなくて困ったという人がいました。気持ちはとても嬉しいけど、実用的には難しかったそうです。
だからこそ、事前の相談が本当に大切なんです。
初節句、実家からのお祝いが事前に聞いてた金額の3倍だった上に、好きなの買いな〜足りなかったらもっと出すから言ってって言われた🥳
— はな🌼☺︎1y (@flower_6020) March 24, 2025
かっこいいやつ買ってあげられる🌟
女の子の初節句で贈るもの
女の子の初節句では、雛人形が定番のお祝いです。
でも、雛人形といってもいろいろな種類があります。
お雛様とお内裏様だけのシンプルな親王飾り、二段飾り、三段飾り、豪華な五段飾りや七段飾りまで、本当にさまざまです。
最近では、住宅事情に合わせてコンパクトなタイプが人気です。玄関やリビングの棚に置ける小ぶりな雛人形や、ケース入りの雛人形なども増えています。
また、ぬいぐるみをお雛様に見立てたものや、モダンなデザインのものも登場していて、選択肢が広がっていますよ。
雛人形以外では、市松人形や羽子板なども伝統的なお祝いの品です。
男の子の初節句で贈るもの
男の子の初節句では、五月人形や兜が代表的なお祝いの品です。
五月人形も、内飾り(兜や鎧を室内に飾るもの)と外飾り(鯉のぼりなど屋外に飾るもの)があります。
最近の住宅事情では、大きな鯉のぼりを庭に立てるのが難しいご家庭も多いですよね。そのため、ベランダに飾れる小さめの鯉のぼりや、室内に飾れる卓上タイプの鯉のぼりも人気です。
兜や鎧も、本格的な大きいものから、コンパクトに飾れるものまで幅広く揃っています。
私の友人は、義両親から「好きなものを選んでいいよ」と言われて、インテリアに合うシンプルな兜を選んだそうです。毎年飾るのが楽しみだと言っていました。
五月人形以外では、武者人形や金太郎の人形なども昔から贈られています。
お祝い金以外で喜ばれるプレゼント
お祝い金や節句飾り以外にも、初節句で喜ばれるプレゼントはたくさんあります。
赤ちゃんの名前入りの食器セットは実用的で記念にもなります。離乳食の時期に使えるものを選ぶと良いですね。
洋服も嬉しいプレゼントです。初節句の記念写真撮影用に、ちょっと特別な服を贈るのも素敵です。
木のおもちゃや知育玩具も人気です。積み木やパズルなど、長く使えるものがおすすめですよ。
カタログギフトを贈って、両親に好きなものを選んでもらうという方法もあります。必要なものを自分で選べるので、実用的ですね。
初節句のお返しは必要?
祖父母からお祝いをもらった場合、基本的にはお返しの品は不要とされています。
でも、感謝の気持ちはしっかり伝えたいですよね。
一番喜ばれるのは、初節句の様子を写真や動画で共有することです。節句飾りと一緒に撮った写真、お祝いの食事会の様子などを送ると、祖父母も嬉しいものです。
私も子どもの初節句の時、義両親に写真をたくさん送りました。特に、贈ってもらった兜と子どもが一緒に写っている写真は、とても喜んでくれましたよ。
お礼の手紙やメッセージカードを添えるのも良いですね。子どもの成長の様子を書いて、感謝の気持ちを伝えましょう。
ちょっとしたプレゼントを贈る場合は、お菓子やお茶などの消え物が無難です。金額的には3分の1から半額程度を目安にすると良いでしょう。
遠方に住んでいる祖父母には、定期的にテレビ電話で赤ちゃんの成長した姿を見せてあげるのも喜ばれます。なかなか会えない分、こうしたコミュニケーションが大切ですね。
食事会はどうする?
初節句では、家族や親戚を招いて食事会を開くのが一般的です。
食事会の場所は、自宅でもレストランでも構いません。赤ちゃんの月齢や参加人数に合わせて決めましょう。
自宅で開く場合は、ちらし寿司やお赤飯など、お祝いらしいメニューを用意すると良いですね。無理をせず、仕出し弁当を頼んだり、デリバリーを利用したりするのもアリです。
レストランで開く場合は、個室があると赤ちゃん連れでも安心です。初節句プランを用意している店も多いので、事前に確認してみてください。
私の経験では、生後6か月くらいだと赤ちゃんもまだ小さいので、自宅でこじんまりとお祝いするのが良かったです。でも、1歳を過ぎてから初節句をする場合は、レストランの個室でゆっくり食事を楽しむのも良いと思います。
食事会の費用は、基本的に赤ちゃんの両親が負担することが多いです。ただし、祖父母が「こちらで出すよ」と申し出てくれる場合もあります。その場合は素直に甘えても大丈夫ですよ。
地域による違いを理解しよう
初節句の祝い方は、地域によってかなり違いがあります。
例えば、関西では母方の祖父母が節句飾りを贈る風習が強く残っている地域もあります。一方、関東では両家で折半することが多いなど、地域差があるんです。
また、節句飾りの種類も地域によって好まれるものが違います。雛人形一つとっても、京雛と関東雛では顔の作りや衣装が異なります。
だからこそ、両家で話し合う時は、それぞれの地域の風習も考慮に入れることが大切です。
「こちらの地域ではこうするのが普通だから」と一方的に決めつけず、お互いの文化を尊重しながら話し合うのが理想的ですね。
兄弟姉妹がいる場合はどうする?
二人目、三人目の子どもの初節句の場合、お祝いをどうするか悩む祖父母も多いです。
基本的には、きょうだいで差が出ないよう、同じようにお祝いをすることが望ましいです。一人目に10万円のお祝いをしたなら、二人目にも同じくらいのお祝いをするのが公平ですね。
ただし、節句飾りについては一人一飾りが基本とされていますが、住宅事情などで難しい場合は、きょうだいで共有することもあります。
その場合は、新しく小ぶりな飾りを追加したり、名前旗を新調したりして、二人目の子どもにも特別感を出すと良いですよ。
おすすめに出産、初節句、お宮参りそれぞれ数十万のお祝いが実家から送られてきた人のツイートが出てきたんだけど、実家太いってこういうことか。出産で義実家から5万ってめちゃくちゃ妥当な一般的な金額だと思う(私的には)けど、実家が太すぎて差を感じてしまうんだな。
— mi☺︎ (@mimama9103) February 23, 2025
今どきの初節句の祝い方
最近の初節句は、昔と比べて柔軟な祝い方が増えています。
SNSで初節句の様子を共有するのも一般的になりました。写真スタジオで記念撮影をして、その写真を祖父母にプレゼントする人も多いです。
また、大きな節句飾りではなく、インテリアに馴染むコンパクトでおしゃれな飾りを選ぶ人が増えています。
私の周りでも、伝統的な雛人形ではなく、木製のシンプルな雛人形を選んだ友人がいました。毎年出し入れしやすくて、インテリアにも合うからとても気に入っているそうです。
食事会も、ホテルの個室やレストランを利用して、少し豪華にお祝いする人が増えていますね。
よくある質問(FAQ)
Q1. 旦那の親からお祝いがない場合、催促してもいい?
お祝いを催促するのは避けた方が良いでしょう。もしかしたら、昔の役割分担の考え方で「父方の祖父母は節句飾りを贈らなくても良い」と思っているのかもしれません。また、食事会の費用を負担するつもりでいたり、後日渡す予定だったりする可能性もあります。気になる場合は、旦那さんに「お祝いについて何か考えているか聞いてみて」と頼むのが良いでしょう。直接的な催促ではなく、確認という形で聞いてもらうのがスマートです。
Q2. 両家の金額に差があっても大丈夫?
金額に差があること自体は、それほど気にしなくても大丈夫です。大切なのは、お祝いしてくれる気持ちです。母方の祖父母が節句飾りを贈り、父方の祖父母が現金でお祝いをする場合など、形が違えば金額に差が出るのは自然なことです。ただし、祖父母同士で金額について話し合っておくと、後々のトラブルを避けられます。夫婦が間に入って、両家の意向を調整する役割を果たすことも大切ですね。
Q3. 節句飾りは誰が買うべき?
昔は母方の祖父母が贈るのが一般的でしたが、現代では必ずしもそうする必要はありません。若い夫婦が自分たちで選んで購入し、費用を両家で折半する方法も増えています。あるいは、一方の祖父母が節句飾りを、もう一方がお祝い金をというように役割を分ける方法もあります。大切なのは、両家で事前に相談して、お互いが納得できる方法を見つけることです。勝手に購入して贈ると、サイズやデザインが合わない可能性があるので、必ず両親に確認しましょう。
Q4. お祝い金はいつまでに渡せばいい?
初節句の1週間から1か月前までに渡すのが一般的です。これは、節句飾りを購入したり、食事会の準備をしたりする時間的な余裕を持たせるためです。特に節句飾りの購入費用として渡す場合は、もっと早めに渡すと親切です。雛人形は1月頃から、五月人形は3月頃から店頭に並び始めるので、それに合わせて年末年始や2月頃に渡すケースも多いですよ。遠方に住んでいる場合は、現金書留で送ることもできます。
Q5. 二人目の初節句のお祝いはどうする?
二人目の初節句でも、基本的には一人目と同じようにお祝いをするのが望ましいです。きょうだい間で差が出ると、後々トラブルの元になる可能性があります。一人目に10万円のお祝いをしたなら、二人目にも同額を贈るのが公平でしょう。節句飾りについては、きょうだいで共有する場合もありますが、その場合は小ぶりな飾りを追加したり、名前旗を新調したりして、二人目にも特別感を出すと良いですよ。
Q6. 食事会に呼ばれなかった場合、どうすればいい?
食事会に呼ばれなかった場合でも、気を悪くする必要はありません。赤ちゃんがまだ小さくて、両親だけでこじんまりとお祝いしたい場合や、コロナ禍の影響で人数を制限している場合もあります。お祝い金や節句飾りを贈って、後日写真や動画を送ってもらう形でも十分です。気になる場合は、「食事会の予定はあるの?」と軽く聞いてみると良いでしょう。もし呼ばれなくても、別の機会にお祝いの気持ちを伝えることができますよ。
「初節句」の人気商品をレビュー件数順に楽天でチェック!まとめ
初節句は、赤ちゃんの健やかな成長を願う大切な行事です。
旦那の親からのお祝い金額の相場は5万円から20万円程度ですが、地域や家庭によって大きく異なります。昔は母方の祖父母が節句飾りを贈り、父方の祖父母が食事会の準備をするという役割分担がありましたが、現代では両家で話し合って柔軟に決めることが増えています。
大切なのは、金額の多さではなく、お祝いする気持ちです。両家で事前に相談して、お互いが納得できる方法を見つけることが、円満な関係を保つ秘訣ですよ。
節句飾りを贈る場合は、必ず赤ちゃんの両親に相談してから選びましょう。住宅事情やインテリアの好みに合わせて、コンパクトなものや現代的なデザインのものを選ぶのも一つの方法です。
お祝いをもらったら、写真や動画で初節句の様子を共有して、感謝の気持ちをしっかり伝えることが大切です。特に遠方に住んでいる祖父母には、こうしたコミュニケーションが喜ばれます。
初めての初節句で不安なこともあるかもしれませんが、家族みんなで子どもの成長を喜び合う素敵な一日にしてくださいね。