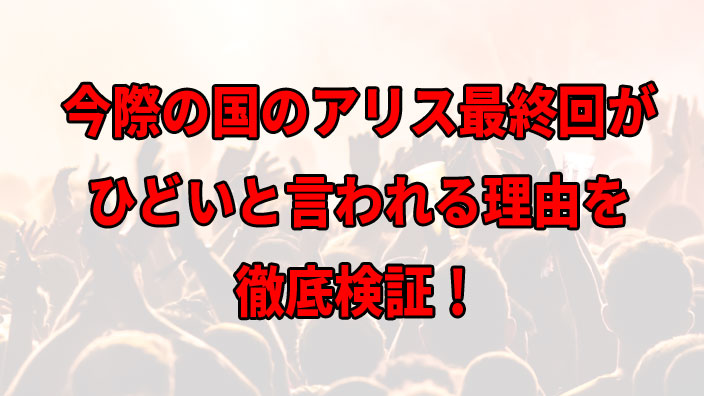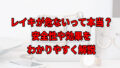Netflix史上最高峰のサバイバルドラマ「今際の国のアリス」。世界中で話題となったこの作品ですが、最終回については賛否が分かれています。特に「ひどい」「つまらない」という厳しい意見も数多く聞かれます。この記事では、なぜ最終回がそう言われるのか、視聴者の本音や口コミを元に詳しく解説していきます。これから見る方も、すでに見た方も、きっと新しい発見があるはずです。
今際の国のアリスとは?基本情報をおさらい
「今際の国のアリス」は、麻生羽呂さんによる大人気漫画が原作です。2010年から2016年まで週刊少年サンデーで連載され、2020年にNetflixで実写ドラマ化されました。
物語は、ゲーム好きの青年アリスが友人と共に異次元の東京「今際の国」に迷い込むところから始まります。そこは生死をかけたゲームに参加しなければ生き残れない恐ろしい世界でした。
主人公のアリス役は山﨑賢人さん、ヒロインのウサギ役は土屋太鳳さんが演じています。Netflix配信後は世界各国で視聴され、日本発のコンテンツとして大きな注目を集めました。
作品の魅力は、スリリングなゲーム展開と人間ドラマが絶妙に組み合わさっていることです。毎回異なるルールのゲームが登場し、参加者たちは知恵と勇気を振り絞って生き残りを図ります。
最終回がひどいと言われる主な理由
今際の国のアリス見終えた。いろいろひどい。でも漫画で最終回を知っているから。うむ。
— Utasinai (@Utasinai) May 3, 2021
現実世界への帰還展開への不満
最も多くの批判が集まっているのが、最終回の現実世界への帰還展開です。多くの視聴者が期待していたのは、今際の国での冒険がどのような形で完結するかでした。
しかし実際は、主人公たちが現実世界に戻り、今際の国での出来事が臨死体験だったという設定が明かされます。この展開に対して「すべてが夢だったのか」という失望感を抱く視聴者が多数いました。
せっかく築き上げた仲間との絆や、命がけで培った成長が、現実では記憶から消えてしまうという設定にも批判が集まりました。視聴者としては、これまで応援してきたキャラクターたちの関係性が無かったことになるような感覚を受けたのです。
伏線回収の不十分さ
作品中に散りばめられた数々の謎や伏線について、最終回での回収が不十分だという声も多く聞かれます。特に今際の国の正体や、なぜそのような世界が存在するのかという根本的な疑問に対する説明が曖昧でした。
視聴者は長時間をかけて作品を追いかけてきたため、すべての謎が明確に解決されることを期待していました。しかし実際は、臨死体験という説明だけで多くの疑問が片付けられてしまい、消化不良を感じる人が多かったのです。
また、個々のキャラクターの背景設定や、ゲームマスターたちの正体についても、もっと詳しい説明を求める声が上がっています。
ジョーカーの登場による混乱
Netflix版では原作にないジョーカーというキャラクターが最後に登場します。このジョーカーの存在により、物語が完全に終わったわけではないことが示唆されますが、この演出が視聴者を混乱させました。
せっかく現実世界に帰還して物語が完結したと思ったところに、新たな謎を提示されることで、「結局何も解決していないのでは」という疑問を抱く人が多くいました。
続編への布石という見方もできますが、一つの作品として見た場合、中途半端な終わり方という印象を与えてしまったのは事実です。
視聴者の口コミと評判を詳しく分析
否定的な意見の傾向
SNSや動画配信サイトのコメント欄を見ると、最終回に対する否定的な意見にはいくつかのパターンがあります。
最も多いのが「夢オチみたいで拍子抜けした」という意見です。長時間かけて築き上げた物語の結末が、すべて臨死体験だったという説明で片付けられることに、多くの視聴者が不満を感じています。
「せっかく感情移入したのに、現実では記憶がリセットされるなんて」という声も数多く見られます。特にアリスとウサギの関係性や、仲間たちとの絆に感動した視聴者ほど、この設定に対する失望が大きいようです。
また「もっと詳しい説明が欲しかった」「謎が残りすぎている」という不完全燃焼感を訴える意見も目立ちます。
肯定的な意見とその理由
一方で、最終回を評価する声もあります。「現実味のある終わり方で良かった」という意見では、臨死体験という設定により、ファンタジー要素が強すぎない現実的な結末になったことを評価しています。
「続編への期待が高まった」という声もあります。ジョーカーの登場により、新たな展開への可能性が示されたことを前向きに捉える視聴者もいるのです。
また「キャラクターの成長が描かれていた」という意見では、現実世界に戻ったアリスたちが、今際の国での経験(記憶はなくても)を活かして前向きに生きていく姿を評価しています。
批判の中での建設的な指摘
批判的な意見の中にも、建設的な指摘が多く含まれています。「もう少し時間をかけて説明してほしかった」という声では、最終回の尺が短すぎることを指摘しています。
「原作との違いをもっと明確にしてほしい」という意見もあります。原作ファンからすると、ドラマ版オリジナルの展開について、もっと丁寧な説明が欲しかったということです。
「キャラクターごとの結末をもっと詳しく見たかった」という声も多く、サブキャラクターたちのその後についても関心が高いことがわかります。
今際の国のアリス見終わった 最終回途中ゲロ吐きそうな程退屈だった🤮
— JuN1ch@脱婆☺︎ (@JuN1ch69) April 27, 2025
シーズン3楽しみだけどね
原作漫画との最終回の違い
基本的なストーリーラインの共通点
原作漫画とNetflix版の最終回は、基本的なストーリーラインは共通しています。今際の国でのゲームをすべてクリアし、永住権を問われ、最終的に現実世界に帰還するという流れは同じです。
主人公アリスの成長や、仲間たちとの絆の描写についても、大筋では原作に沿った展開となっています。現実世界で医師として働くアリスの姿も、原作の設定を踏襲しています。
Netflix版独自の演出と追加要素
しかし、Netflix版には独自の演出が数多く加えられています。最も大きな違いは、ジョーカーの登場です。原作では明確に物語が完結しますが、Netflix版では続編への可能性を残す演出となっています。
また、現実世界での病院のシーンも、Netflix版の方がより詳細に描かれています。隕石落下事故の被害状況や、医療チームの対応なども丁寧に映像化されています。
キャラクター同士の関係性についても、Netflix版では原作以上に深く掘り下げられている部分があります。特にアリスとウサギの恋愛関係は、Netflix版の方がより印象的に描かれています。
ファンの原作派とドラマ派の意見対立
原作ファンの中には、Netflix版の独自要素に対して批判的な意見を持つ人もいます。「原作の完結感が薄れた」「余計な要素を加えすぎ」という声が聞かれます。
一方で、Netflix版から作品を知った視聴者は、映像化による迫力や演出を高く評価しています。「原作よりも感情移入しやすかった」「キャラクターの魅力が増した」という意見もあります。
このような意見の対立も、最終回への評価が分かれる一因となっています。どちらの立場から見るかによって、同じシーンでも全く違った印象を受けるのです。
臨死体験設定への賛否両論
臨死体験という設定の意味
今際の国が臨死体験中の世界だったという設定は、作品のテーマと深く関わっています。生と死の境界線で繰り広げられる物語だからこそ、登場人物たちの生への執着や、仲間への思いがより強く描かれるのです。
この設定により、ゲームでの死が本当の死を意味することの重さも表現されています。参加者たちが必死に生き残ろうとする理由も、単なるゲームではなく、現実の生死に直結しているからです。
また、現実世界に戻った時の喪失感も、この設定があるからこそ表現できる感情です。大切な記憶を失いながらも、どこか懐かしさを感じる複雑な心境は、臨死体験という設定なしには描けません。
視聴者が感じる違和感の正体
しかし多くの視聴者が感じる違和感も理解できます。長時間かけて積み重ねた物語が、「すべて夢でした」のような形で片付けられることへの抵抗感は自然な反応です。
特に、今際の国での成長や絆が現実世界では記憶として残らないという設定は、視聴者の感情投資を無駄にしたような印象を与えてしまいます。
また、臨死体験にしては世界観が詳細すぎるという指摘もあります。ゲームのルールや、今際の国の社会システムなど、個人の意識だけで作り出すには複雑すぎるという意見です。
現実味のある解釈の可能性
一方で、臨死体験という設定に現実味を感じる視聴者もいます。実際の臨死体験者の証言には、非常に鮮明で現実的な体験談が多く含まれているからです。
医学的にも、脳の活動が停止寸前の状態で、非常に鮮明な意識体験が起こることが報告されています。今際の国の世界観も、そのような状態で生じる意識体験として捉えれば、十分に説得力があります。
また、現実世界でアリスが医師として働いているという設定も、臨死体験を通じて生命の尊さを学んだ結果として自然に感じられます。
他の登場人物たちの最終的な運命
主要キャラクターたちのその後
最終回では、今際の国で共に戦った仲間たちが、現実世界でどのような状況にあるかが描かれます。チョータやカルベといった親友たちも、病院で治療を受けている姿が映されます。
ウサギ(ユズハ)は、現実世界でもアリスと出会い、お互いに何か懐かしいような感覚を抱きます。記憶はないものの、魂レベルでの繋がりを感じさせる演出となっています。
ニラギやアグニなど、今際の国で重要な役割を果たしたキャラクターたちも、現実世界での姿が描かれ、それぞれが新しい人生を歩んでいることが示されます。
生存者と犠牲者の運命の分かれ道
今際の国で生き残ったキャラクターは現実世界でも生存し、ゲームで死亡したキャラクターは現実でも命を落とすという設定になっています。
これにより、今際の国での選択や行動が、現実の生死に直結していたことが明確になります。ゲームでの死が単なるフィクションではなく、本当の意味での生死の分かれ目だったのです。
一方で、今際の国で死亡したキャラクターのファンからは、「もっと救済のある結末にしてほしかった」という声も上がっています。特に人気の高いキャラクターについては、その死に納得できない視聴者も多いようです。
記憶を失った者たちの新しい関係性
現実世界に戻ったキャラクターたちは、今際の国での記憶を失っています。しかし、なぜか惹かれ合う感覚や、既視感のような感情を抱くことが描かれています。
アリスとウサギの関係がその典型例で、初対面のはずなのに自然に会話が弾み、お互いに特別な感情を抱きます。この演出は、魂レベルでの繋がりの存在を示唆しています。
ただし、この設定についても賛否が分かれています。「ロマンチックで良い」という意見がある一方で、「都合が良すぎる」という批判的な声もあります。
なぜ最終回の評価が分かれるのか
期待値と実際のギャップ
最終回への評価が分かれる最も大きな理由は、視聴者の期待値と実際の内容のギャップです。多くの視聴者は、今際の国の謎がすべて解明され、スッキリとした結末を期待していました。
しかし実際は、臨死体験という説明で多くの謎が片付けられ、新たにジョーカーという謎も提示されました。期待していた完結感が得られなかった視聴者が、失望を表現しているのです。
一方で、続編への可能性や、現実的な解釈を求めていた視聴者は、この結末を評価しています。同じ内容でも、何を期待していたかによって評価が180度変わるのです。
物語の解釈の多様性
「今際の国のアリス」という作品は、多様な解釈が可能な構造になっています。臨死体験として捉えることもできれば、パラレルワールドとして解釈することも可能です。
このような多様性は作品の魅力でもありますが、同時に評価が分かれる原因でもあります。視聴者それぞれが異なる解釈をするため、同じシーンでも全く違った感想を持つのです。
また、原作とドラマ版の違いも、評価の分かれる要因となっています。どちらを基準にするかによって、最終回への評価も変わってきます。
個人の価値観による影響
最終的には、個人の価値観や人生経験が、作品への評価に大きく影響します。生死について深く考えたことがある人は、臨死体験という設定により感動するかもしれません。
一方で、エンターテイメントとしてのスッキリ感を重視する人は、謎が残る結末に不満を感じるでしょう。どちらが正しいということはなく、それぞれの感じ方があって当然です。
年齢や人生経験によっても、作品への感じ方は変わります。若い視聴者は冒険要素を重視し、年配の視聴者は人生観の描写に注目するといった違いもあります。
今際の国のアリス見終わったけど最後のジョーカーの考察が『人生』ってのが全然意味わかんないんで終わりです。最終回ほんとネムカッタ。。
— さるすた (@sarustar_GANG) January 16, 2023
最終回を楽しむための視点
作品のテーマを理解する
最終回をより楽しむためには、作品全体のテーマを理解することが重要です。「今際の国のアリス」は単なるサバイバルゲームの物語ではなく、生きることの意味を問う作品です。
主人公アリスの成長物語として見れば、現実世界での医師としての道も、今際の国での経験が活かされた結果として理解できます。記憶はなくても、魂レベルでの成長は残っているのです。
また、仲間との絆についても、現実世界での再会シーンで新たな形で描かれています。完全に失われたわけではなく、形を変えて続いていると解釈できます。
映像美と演出の質の高さ
Netflix版の最終回は、映像美と演出の質の高さでも評価されています。現実世界と今際の国の対比や、病院でのリアルな医療シーンなど、映像作品としての完成度は非常に高いです。
特に、アリスとウサギの再会シーンは、多くの視聴者の心を打ちました。言葉では表現できない感情が、映像と音楽で見事に表現されています。
キャスト陣の演技力も、最終回の魅力の一つです。山﨑賢人さんと土屋太鳳さんの自然な演技により、複雑な感情が丁寧に描かれています。
続編への期待と可能性
ジョーカーの登場により、続編への可能性が示されています。実際に、シーズン3の制作も発表されており、新たな展開への期待が高まっています。
最終回で残された謎も、続編で解明される可能性があります。一つの作品として見れば未完成でも、シリーズ全体で見れば序章に過ぎないかもしれません。
このような長期的な視点で見れば、最終回への評価も変わってくるでしょう。一時的な完結感よりも、物語全体の壮大さを楽しむことができます。
実際に視聴した体験談
私自身も「今際の国のアリス」の大ファンとして、最終回には複雑な思いを抱きました。シーズン1から追いかけてきた物語の結末に、正直なところ戸惑いを感じたのも事実です。
特に印象的だったのは、アリスとウサギが現実世界で再会するシーンでした。記憶はないはずなのに、なぜか懐かしい感覚を抱く二人の表情が印象的で、胸が熱くなりました。
一方で、今際の国の謎についてもっと詳しい説明が欲しかったというのも本音です。長時間かけて築き上げた世界観だからこそ、すべてを理解したいという欲求がありました。
しかし、何度か見返すうちに、この終わり方にも意味があることが分かってきました。すべてを説明しないからこそ、視聴者それぞれが自分なりの解釈を持てるのです。
友人たちとの議論も楽しく、同じ作品を見ても全く違う感想を持つことに驚きました。それだけ奥深い作品だということでもあります。
「今際の国のアリス」の人気商品をレビュー件数順に楽天でチェック!まとめ
「今際の国のアリス」の最終回が「ひどい」と言われる理由は、主に以下の点に集約されます。
臨死体験という設定による夢オチ感、伏線回収の不十分さ、ジョーカー登場による新たな謎の提示、期待値と実際の内容のギャップ、そして視聴者の価値観や解釈の違いです。
しかし一方で、現実味のある結末、映像美と演出の質の高さ、キャラクターの成長描写、続編への可能性なども評価されています。
最終的には、この作品をどのような視点で見るかによって、評価は大きく変わります。完璧な答えを求める人には物足りないかもしれませんが、多様な解釈を楽しめる人には魅力的な作品です。
重要なのは、批判的な意見も肯定的な意見も、どちらも作品への愛情から生まれているということです。それだけ多くの人に影響を与えた作品だからこそ、様々な意見が飛び交うのです。
これから視聴する方は、様々な意見があることを知った上で、自分自身の感想を大切にしてください。きっと、あなただけの「今際の国のアリス」の解釈が見つかるはずです。