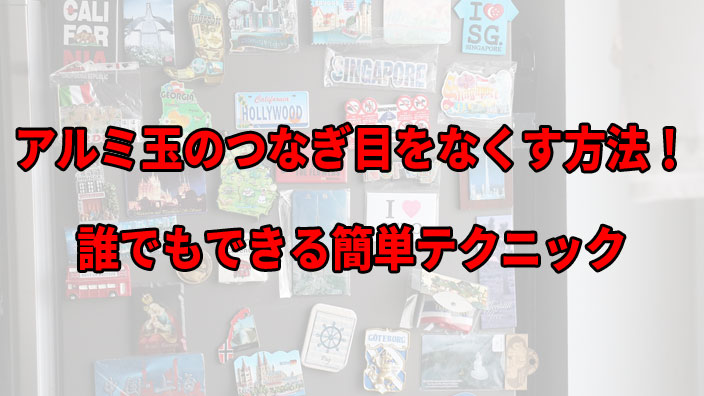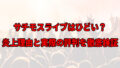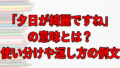SNSで大人気のアルミ玉作り。でも、つなぎ目が目立ってしまって困っていませんか?実は私も最初、つなぎ目がヒラヒラしてしまってかなり苦労しました。この記事では、アルミ玉のつなぎ目をきれいになくす方法を、誰でも実践できるように詳しく解説します。最後まで読めば、鏡のようにピカピカのアルミ玉が作れるようになりますよ。
アルミ玉のつなぎ目とは?なぜできるのか
アルミ玉作ってるなぅ。
— ®春にゃんすけ(=| ´ㅅ` |=)🌷 (@haru86new) February 18, 2022
アルミ玉作ったことある人いるかな?つなぎ目どーやって消すの💦 pic.twitter.com/LQYxXZTHGk
アルミ玉作りで一番困るのが「つなぎ目」の存在です。つなぎ目というのは、アルミホイルを丸めたときに最後の端っこの部分が浮き上がってきて、ヒラヒラした状態になってしまう現象のことです。
私も最初に作ったとき、丸めた後にハンマーで叩いていたら、端っこの部分がペロッとめくれ上がってきて「あれ?これどうするの?」って焦った記憶があります。この部分をそのままにしておくと、どんなに叩いても綺麗な球体にならないんですよね。
つなぎ目ができる原因は主に2つあります。1つ目は、アルミホイルを丸めるときに綺麗に巻きすぎてしまうこと。実は、きっちり巻きすぎると各層がしっかり絡み合わないので、最後の部分が剥がれやすくなってしまうんです。2つ目は、叩く力が強すぎること。形が整ってきた後に強く叩きすぎると、つなぎ目が浮き上がってきてしまいます。
つなぎ目があると見た目が悪いだけじゃなくて、叩いてもその部分だけフワッと浮いてきてしまって、なかなか球体が綺麗に仕上がりません。だからこそ、つなぎ目をなくす技術が重要なんです。
つなぎ目をなくす基本テクニック
つなぎ目をなくすための基本的な方法をご紹介します。実際に私が試して効果があった順番で説明していきますね。
ヒラヒラ部分をカットする方法
まず最初にやるべきことは、ヒラヒラしている部分をはさみかカッターで切り取ることです。つなぎ目がヒラヒラしてしまっている場合、そのままだとなかなかくっつきません。私も最初は「叩けば何とかなるだろう」と思って放置していたんですが、全然ダメでした。
ヒラヒラの部分は思い切って切ってしまいましょう。切るときのコツは、できるだけ球体に沿うように、余分な部分だけを切り取ることです。あまり深く切りすぎると、今度は切った跡が目立ってしまうので注意が必要です。
切った後は、その部分をひたすら叩きます。このときも最初は優しく、徐々に力を入れていくのがポイントです。急に強く叩くと、つなぎ目が逆に目立ってしまうことがあります。
折り返して叩く方法
子供の夏休みにちょっと前に流行ったアルミ玉を作ることになりました😂
— チャンネルあきMy Home Recovery (@hirasawanoriaki) July 26, 2024
ヒカキンさんのアルミ玉を一緒に見てからやりたくなったらしい😅w pic.twitter.com/LPJWwzoCPR
次に効果的なのが、つなぎ目の部分を内側に折り曲げて叩く方法です。これは人気YouTuberのヒカキンさんも紹介している方法で、実際にかなり効果があります。
やり方は簡単です。つなぎ目やめくれている部分を手で慎重に内側に折り曲げます。このとき、一気に折り曲げようとすると破れてしまう可能性があるので、少しずつ様子を見ながら折り曲げていきましょう。
折り曲げた部分を金づちやハンマーでコツコツと叩いていきます。この作業は本当に根気が必要で、私は30分くらいかけて少しずつ叩き続けました。でも、この地道な作業がつなぎ目をなくす一番確実な方法なんです。
叩くときのコツは、つなぎ目だけを集中的に叩くのではなく、周りも含めて全体的に叩いていくことです。そうすることで、つなぎ目の部分が自然に周りと馴染んでいきます。
叩く力加減の調整
つなぎ目をなくすためには、叩く力加減がとても重要です。私の失敗談なんですが、最初は「強く叩けば早く固まるだろう」と思って、ガンガン叩いていたんですよね。そしたら、つなぎ目がどんどん目立つようになってしまって、逆効果でした。
最初は柔らかいので、優しく叩いて徐々に固めていきます。形が整ってきたら、少しずつ力を強くしていく感じです。特にアルミ玉がある程度硬くなってきた後は、それほど力を入れる必要はありません。軽めにコツコツと叩いていくだけで十分です。
強く叩きすぎると、つなぎ目が目立つ原因になってしまいます。丁寧に、愛情を込めて叩いていくことが大切です。ヒカキンさんも「アルミ愛が大事」って言っていましたが、本当にその通りだと思います。
つなぎ目を予防するコツ
つなぎ目をなくす方法も大事ですが、そもそもつなぎ目ができにくくする予防策も知っておくと便利です。
丸め方の工夫
つなぎ目を予防する一番のポイントは、最初の丸め方です。アルミホイルを丸めるとき、端っこを綺麗に巻きすぎないことが重要です。これ、意外と知られていないんですよね。
綺麗に巻きすぎると、各層がしっかり絡み合わないので、後でつなぎ目が剥がれやすくなってしまいます。端の部分は、指でしっかり隙間に押し込みながら、他の部分としっかり絡み合うようにしておきましょう。
具体的には、アルミホイルをふわっと巻き付けていく感じです。表面がボコボコになるくらいでちょうどいいんです。そうすることで、各層が複雑に入り組んで、後から剥離することがなくなります。
私は最初、「綺麗に巻かなきゃ」って思って、ピシッときっちり巻いていました。でもそれが逆効果だったんです。今では、わざとシワシワにしながら丸めるようにしています。
アルミホイルを切らずに使う
アルミホイルを丸めるときは、できるだけ切らずに1枚のまま使うことをおすすめします。途中で切れてしまうと、その部分がつなぎ目になってしまう可能性があります。
切れても大丈夫なんですが、切れた部分が玉の表面に出てくると、つなぎ目として叩いてもふわっと浮いてきてしまいます。だから、最初から切らないように気をつけながら丸めていくのがベストです。
もし途中で切れてしまった場合は、その部分を内側に折り込むようにして、表面に出ないようにしましょう。丸める段階でこの処理をしておくだけで、後の作業がずっと楽になります。
ザラザラした面でこする方法
ハンマーで叩くだけでは限界があります。より綺麗に仕上げるためには、ザラザラした面でこする方法も試してみましょう。
机の板面を使う方法
ハンマーで叩き続けるのって、けっこう疲れるんですよね。私も何時間も叩き続けて、腕がパンパンになったことがあります。そんなときに効果的なのが、ザラザラした机の板面でこする方法です。
机の板面がちょっとザラザラしている場合、その上でアルミ玉をゴロゴロと転がすように擦ってみてください。これが意外と効果があるんです。つるつるの机では全然効果がないので、必ずザラザラした面を使いましょう。
この方法の良いところは、ハンマーで叩くよりも腕が疲れないことです。しかも、球体全体を均一に削っていけるので、バランスよく仕上がります。私は叩く作業に疲れたら、この方法で休憩がてら磨くようにしています。
ただし、あまり強く擦りすぎると表面に傷がついてしまうので、適度な力加減で行いましょう。軽く円を描くようにゴロゴロと転がす感じがちょうどいいです。
紙やすりで磨く方法
小学2年の息子が16メートルのアルミホイルを材料に、6時間かけて作ったアルミの玉。
— 和也じゃない方 (@M22414507) December 20, 2019
金槌で叩いて2時間。紙やすりを2時間。金属研磨剤で2時間。
こんなことする人がまさか身近にいるとは思わなかった pic.twitter.com/ozSIJ54r3S
つなぎ目をなくして、さらにピカピカに仕上げるためには紙やすりが必須です。
荒い目から細かい目へ順番に磨く
紙やすりを使うときの基本は、荒い目から細かい目へと順番に磨いていくことです。これを守らないと、綺麗な仕上がりにならないんです。
まずは粗い目(#120や#240くらい)の紙やすりで、表面の大きな凸凹を削っていきます。このときに、つなぎ目の部分も集中的に磨いていきましょう。荒い目の紙やすりでしっかり磨くことで、つなぎ目が目立たなくなります。
荒い目である程度滑らかになったら、次は中くらいの目(#400くらい)で磨きます。そして最後に細かい目(#1000以上)で仕上げていきます。この段階を踏むことで、大きな傷を小さな傷で消していくイメージです。
私の経験上、特に重要なのは最初の荒い目でしっかり磨くことです。ここで手を抜くと、後でいくら細かい目で磨いても綺麗にならないんです。時間はかかりますが、焦らず丁寧に磨いていきましょう。
耐水ペーパーの使い方
紙やすりの中でも、特におすすめなのが耐水ペーパーです。普通の紙やすりとの違いは、水をつけながら使えることと、アルミの削りカスが入りにくいことです。
耐水ペーパーは#1000、#2000、#3000と、かなり細かい目のものがあります。これを使うと、鏡のような仕上がりに近づけることができます。
使い方のコツは、全体を少しずつ細かく磨いていくことです。つなぎ目だけを集中的に磨くのではなく、球体全体を均一に磨いていくイメージです。そうすることで、つなぎ目が自然と馴染んでいきます。
耐水ペーパーで磨く作業は腕が疲れます。私も最初は「早く終わらせたい」と思って一気にやろうとしたんですが、無理でした。休憩を挟みながら、少しずつ時間をかけて磨くのがおすすめです。
研磨剤で仕上げる方法
紙やすりで磨いた後は、研磨剤を使って最終仕上げをします。ここまでくれば、つなぎ目はほとんど目立たなくなっているはずです。
ピカールケアがおすすめ
研磨剤の中でも、特におすすめなのが「ピカールケア」です。これは半固形タイプの研磨剤で、液だれしないので使いやすいんです。ヒカキンさんも「チート級」って言っていましたが、本当にその通りです。
ピカールケアを柔らかい布につけて、アルミ玉を磨いていきます。円を描くようにクルクルと磨いていくと、どんどん輝きが増していきます。つなぎ目があった部分も、この段階でほぼ見えなくなります。
研磨剤を使う前と使った後では、輝き方が全然違います。私も最初に使ったときは「え、こんなに変わるの!?」って驚きました。まるで金属の塊みたいにピカピカになります。
ただし、研磨剤を使いすぎると表面を削りすぎてしまうので注意が必要です。適度な量を使って、優しく磨いていきましょう。
クリーム状の研磨剤の使い方
ピカール以外にも、クリーム状の研磨剤がいろいろあります。初心者の方には、クリーム状のものが使いやすいと思います。
クリーム状の研磨剤を使うときは、柔らかい布やスポンジに少量つけて磨きます。つなぎ目があった部分を中心に、全体を均一に磨いていきましょう。
研磨剤で磨く作業は、紙やすりほど力を入れる必要がありません。軽く撫でるように磨いていくだけで、徐々に輝きが出てきます。焦らず、じっくりと磨いていくことが大切です。
つなぎ目を目立たなくするための叩き方
つなぎ目をなくすためには、正しい叩き方を知っておくことが重要です。
ゴムハンマーと金づちの使い分け
アルミ玉を作るときに使う道具として、ゴムハンマーと金づちがあります。どちらを使うべきか迷っている人も多いと思います。
ゴムハンマーは、叩いたときに跡が残りにくいという利点があります。特に平面タイプのゴムハンマーを使うと、滑らかな表面に仕上がりやすいです。ただし、重いので長時間使っていると腕が疲れます。
一方、金づちは軽いので扱いやすいです。私は普通の金づちを使っていますが、特に問題なく作れています。金づちを使うときは、叩く面ができるだけきれいなものを選びましょう。
個人的には、最初は金づちで圧縮して、ある程度形が整ってきたらゴムハンマーに切り替える方法がおすすめです。でも、金づち一本でも十分綺麗に作れるので、わざわざゴムハンマーを買う必要はないと思います。
全体を均一に叩くコツ
つなぎ目を目立たなくするためには、球体全体を均一に叩くことが重要です。一箇所だけを集中的に叩いていると、形がいびつになってしまいます。
叩くときは、アルミ玉を回しながら、表面全体を隙間なく叩いていきましょう。これが一番面倒な作業なんですが、仕上がりに直結する重要なポイントです。
私はテレビを見ながら無心で叩いています。30分から1時間くらいは叩き続けることになるので、何か楽しみながらやるのがおすすめです。音楽を聴きながらでもいいですし、好きな動画を見ながらでもOKです。
叩く位置を少しずつずらしながら、丁寧に全体を叩いていきましょう。この地道な作業が、美しいアルミ玉を作る秘訣です。
柔らかい場所から硬い場所へ
最初は柔らかい場所で叩き始めることをおすすめします。ラグや絨毯の上などで叩きながら、徐々に固くしていくイメージです。
柔らかい場所で叩くことで、中の空気が抜けて圧縮されていきます。この段階でしっかり圧縮しておかないと、後でつなぎ目が浮き上がってきやすくなります。
ある程度固まってきたら、硬い場所(机の上など)に移して叩き続けます。このときも、急に強く叩くのではなく、徐々に力を入れていくことが大切です。
アルミ玉作りで失敗しないための注意点
つなぎ目をなくすために、いくつか注意すべきポイントがあります。
最初の成型が重要
アルミ玉を綺麗に作るコツは、最初の成型段階で綺麗に作ることです。実は、途中でもご紹介しましたが、成型の段階が最も大切なんです。
最初に適当に丸めてしまうと、後でいくら叩いても綺麗な球体にはなりません。形が歪んでしまうと、修正するのがとても難しいんです。
だからこそ、最初の丸める段階で、できるだけ綺麗な球体を作るように意識しましょう。時間をかけて丁寧に丸めることが、後の作業を楽にしてくれます。
強く叩きすぎない
つなぎ目を消そうとして、強く叩きすぎるのは逆効果です。特に形が整ってきた後に強く叩くと、つなぎ目が目立つ原因になってしまいます。
最初は柔らかいので様子を見ながら優しく叩いて、徐々に力を強くしていきましょう。形が崩れないように注意しながら、丁寧に叩いていくことが大切です。
インターネット上では「あまり叩かない方がいい」という記事もありますが、それは間違いです。叩く回数自体は多くても大丈夫です。大事なのは力加減です。
手袋とマスクを着用する
アルミ玉を作る作業中は、手袋とマスクを着用することをおすすめします。素手で作業していると、手が真っ黒になってしまうんです。
私も最初は何も考えずに素手で作業していたんですが、気づいたら手が黒くなっていて、石鹸で洗っても全然落ちませんでした。それ以来、必ず作業用の手袋をつけるようにしています。
また、作業中にアルミホイル特有の匂いがしてくることがあります。人によっては気分が悪くなることもあるので、マスクを着用した方が安心です。
厚手の軍手を使えば、金づちが手に当たったときの怪我防止にもなります。安全に作業するためにも、手袋とマスクは必須アイテムです。
宿題やらずに、アルミ玉を作る子に伝える言葉が母にはない。 pic.twitter.com/97lmNCrSqv
— 七ツ箱 (@nanatsubaco) August 16, 2025
つなぎ目がどうしても消えないときの対処法
いろいろ試してもつなぎ目が消えない場合の最終手段をご紹介します。
思い切ってやり直す
つなぎ目がどうしても消えない場合、思い切ってやり直すのも一つの方法です。特に最初の成型段階でミスをしてしまった場合は、後でいくら頑張っても綺麗にならないことがあります。
私も一度、つなぎ目があまりにも目立つので、途中で諦めてやり直したことがあります。最初は「もったいない」と思ったんですが、やり直した方が結果的に時間も短縮できました。
アルミホイルはそれほど高価なものではないので、失敗したら新しく作り直すのもありです。その失敗から学んだことを次に活かせば、2回目はもっと上手に作れるはずです。
割れ目も同じ方法で対処
つなぎ目だけでなく、割れ目ができてしまうこともあります。割れ目が出来た場合も、基本的につなぎ目と同じ対処法で大丈夫です。
角が出ている部分を慎重に手で折り曲げながら、金づちで叩いていきましょう。力の入れ方には十分注意して、少しずつ目立たなくしていきます。
割れ目の場合は、周りよりも圧縮が足りていない可能性があります。その部分を重点的に叩いて、周りと同じくらいの硬さにしていきましょう。
アルミ玉作りに必要な時間
つなぎ目をきれいになくして、ピカピカのアルミ玉を作るには、どのくらいの時間がかかるのでしょうか。
工程別の所要時間
アルミホイルを丸める作業は、10分から15分くらいです。ここは丁寧にやることが重要なので、焦らずじっくり時間をかけましょう。
ハンマーで叩く作業は、一番時間がかかります。少なくとも1時間から2時間は見ておいた方がいいです。私の場合、つなぎ目をなくすのに特に時間がかかって、2時間半くらいかかりました。
紙やすりで磨く作業も時間がかかります。荒い目から細かい目まで順番に磨いていくと、1時間から2時間は必要です。こだわりがある場合は、もっと長くかかることもあります。
研磨剤で仕上げる作業は、30分から1時間くらいです。ここまでくれば、もうゴールは目の前です。
トータルでどのくらいかかる?
全部合わせると、最低でも3時間から4時間は見ておいた方がいいです。もっとピカピカに仕上げたい場合は、6時間以上かかることもあります。
ヒカキンさんは2日間かけて作っていましたが、それくらい時間をかけた方が、確実に綺麗な仕上がりになります。
一気に全部やろうとすると疲れてしまうので、何日かに分けて作業するのがおすすめです。私は週末を使って、土曜日に叩く作業、日曜日に磨く作業というふうに分けて作りました。
時間に余裕があるときに作りましょう。そうしないと、続きが気になって他のことに集中できなくなってしまいます。
アルミ玉を綺麗に作るためのプロのコツ
より完成度の高いアルミ玉を作るための上級テクニックをご紹介します。
鏡面仕上げを目指す
鏡のように顔が映るほど磨いたものを「鏡面仕上げ」といいます。これを目指すなら、かなり細かい番手のコンパウンドまで使う必要があります。
紙やすりで#3000まで磨いた後、さらに細かい粒子のコンパウンド(#30000くらい)で磨いていきます。ここまでやると、相当な時間と労力がかかりますが、やり切ったときの達成感は半端じゃないです。
鏡面仕上げにするためには、大きな傷を小さな傷で消していく作業を複数回行います。極限まで小傷を消すことで、フラットな面ができあがり、顔が映り込むほどの輝きが得られます。
アルミホイルの量を調整する
作りたいアルミ玉の大きさによって、アルミホイルの量を調整しましょう。8メートルのアルミホイルで、だいたい直径5センチくらいのアルミ玉ができます。
10メートルのアルミホイルを使った場合、最終的な仕上がりは野球ボールくらいの大きさになります。ただし、磨く工程で削れていくので、最初に思っているよりも小さくなることを覚えておきましょう。
初心者の方は、まず小さめのサイズから始めることをおすすめします。大きいアルミ玉ほど完成までに時間がかかるので、最初は5センチくらいのミニサイズで練習するのがいいと思います。
光っている面を外側にする
アルミホイルには、光っている面とマットな面があります。丸めるときは、光っている面を外側にするのがポイントです。
光っている面の方が、磨いたときに輝きやすいんです。私も最初、どっちでもいいかなと思って適当に丸めていたんですが、やっぱり光っている面を外にした方が仕上がりが綺麗でした。
細かいことですが、こういった小さな工夫の積み重ねが、最終的な仕上がりの差になります。
アルミ玉作りの楽しみ方
つなぎ目をなくして綺麗なアルミ玉を作る過程は、実は意外と楽しいものです。
無心になれる作業
アルミ玉作りは、ひたすら叩いたり磨いたりする地道な作業の連続です。でも、この単純作業が意外と心地いいんですよね。
無心でコツコツと作業していると、日頃のストレスや悩みを忘れることができます。私も仕事で疲れているときに作ったんですが、作業に集中しているうちに気分がリフレッシュしました。
瞑想みたいな効果があるのかもしれません。何も考えずに、ただアルミ玉と向き合う時間は、意外と貴重です。
完成したときの達成感
つなぎ目を完全になくして、ピカピカのアルミ玉が完成したときの達成感は最高です。何時間もかけて作り上げたものを手に取って、鏡のように自分の顔が映っているのを見たときは、思わず「やった!」って声が出ました。
特に、最初は「これ本当にできるのかな?」って半信半疑だったのが、自分の手で完璧なアルミ玉を作れたときの感動は忘れられません。
SNSにアップすれば、たくさんの人が反応してくれます。私も友達に見せたら「すごい!どうやって作ったの?」って興味津々で聞かれました。
子供と一緒に楽しめる
アルミ玉作りは、子供と一緒に楽しめるクラフトでもあります。危険な作業もありますが、大人が見守りながらやれば、親子で楽しい時間を過ごせます。
叩く作業は子供も楽しめます。ただし、指を叩かないように注意が必要ですし、研磨剤を使う作業は大人がやった方が安全です。
夏休みの自由研究にもぴったりです。作る過程を写真に撮って記録すれば、立派な研究作品になります。
アルミ玉の保管方法
せっかく作ったアルミ玉、できるだけ綺麗な状態で保管したいですよね。
酸化を防ぐ方法
アルミは空気に触れると酸化して、徐々にくすんでしまいます。できるだけ空気に触れないように保管することが大切です。
ジップロックなどの密閉袋に入れて保管するのがおすすめです。さらにシリカゲルなどの乾燥剤を一緒に入れておくと、より長期間綺麗な状態を保てます。
私は透明なケースに入れて飾っていますが、定期的に柔らかい布で拭いて、表面の汚れを取るようにしています。
再び磨き直す方法
時間が経ってくすんでしまった場合でも、研磨剤で磨き直せば元の輝きを取り戻せます。定期的にメンテナンスすることで、いつまでも綺麗な状態を保つことができます。
くすみが気になったら、ピカールケアなどの研磨剤で軽く磨いてみてください。新品のような輝きが戻ってきます。
アルミ玉作りで使える道具
つなぎ目をなくして綺麗なアルミ玉を作るために、あると便利な道具をまとめました。
必須の道具
絶対に必要なのは、アルミホイル、ハンマー(金づちまたはゴムハンマー)、紙やすり(#120、#400、#1000以上)、研磨剤(ピカールケアなど)です。
これらがあれば、基本的なアルミ玉は作れます。ホームセンターで全て揃うので、買い物も簡単です。
あると便利な道具
耐水ペーパー(#2000、#3000)があると、より綺麗に仕上がります。特に鏡面仕上げを目指す場合は必須です。
作業用の手袋とマスクも、快適に作業するために重要です。厚手の軍手なら、金づちから手を守ってくれます。
柔らかい布やクロスも何枚か用意しておきましょう。研磨剤を使うときに必要です。古いTシャツなどを切って使っても大丈夫です。
大人の夏休み自由研究2
— ゆずるん77🐞+ (@Yuzurun610) August 15, 2022
結構前だけどHIKAKINさんのアルミ玉の動画見ていつか作ってみたいと思ってたんよ😌磨けばもうちょい光りそう(きれいに作るのかなりムズイ) pic.twitter.com/BFdLzKaQ8z
アルミ玉作りに関するよくある質問
Q1. つなぎ目が完全になくならないのですが、どうすればいいですか?
つなぎ目が完全になくならない場合は、以下のステップを試してみてください。まず、つなぎ目の浮いている部分を丁寧にカッターで切り取ります。次に、その部分を内側に折り曲げて、周りと馴染ませます。そして金づちで優しく叩いて圧縮していきます。
それでもまだ目立つ場合は、荒い目の紙やすりで集中的に削っていきましょう。つなぎ目の部分だけを削るのではなく、周囲も含めて広めに削ることで、自然に馴染んでいきます。最後に研磨剤で磨けば、ほとんど見えなくなるはずです。
どうしても消えない場合は、最初の成型段階に問題があった可能性があります。新しく作り直す方が、結果的に時間の節約になることもあります。
Q2. アルミ玉を作るのにどのくらい時間がかかりますか?
初めて作る場合、完成までに4時間から6時間程度かかると考えておきましょう。慣れてくれば3時間くらいで作れるようになります。
ただし、鏡面仕上げを目指す場合は、さらに時間がかかります。プロ級の仕上がりを目指すなら、2日間くらいかけてじっくり作ることをおすすめします。
一気に全部やろうとすると疲れてしまうので、何日かに分けて作業するのがいいですよ。私は週末を使って、初日に叩く作業、2日目に磨く作業をしています。
Q3. ゴムハンマーと金づち、どちらがいいですか?
どちらでも綺麗なアルミ玉は作れます。ゴムハンマーは表面に跡が残りにくいという利点がありますが、重いので長時間使うと腕が疲れます。
金づちは軽くて扱いやすいです。表面に小さな跡がつくことがありますが、後で紙やすりで削れば問題ありません。私は普通の金づちを使っていますが、特に不便は感じていません。
両方持っている場合は、最初は金づちで圧縮して、形が整ってきたらゴムハンマーに切り替えるのもいい方法です。でも、わざわざゴムハンマーを買う必要はないと思います。
Q4. アルミホイルは何メートル必要ですか?
作りたいサイズによって変わってきます。直径5センチくらいの小さめサイズなら、8メートルから10メートルのアルミホイルで作れます。
野球ボールくらいのサイズを作りたい場合は、15メートルから20メートルくらい必要です。ただし、最終的に磨く工程で削れていくので、最初に思っているよりも小さくなります。
初心者の方は、まず小さめのサイズから挑戦することをおすすめします。小さい方が完成までの時間も短いですし、失敗しても気軽にやり直せます。
Q5. 紙やすりは何番を使えばいいですか?
基本的には、荒い目(#120または#240)、中くらいの目(#400)、細かい目(#1000以上)の3種類を用意しましょう。
より綺麗に仕上げたい場合は、耐水ペーパーの#2000、#3000も追加するといいです。鏡面仕上げを目指すなら、さらに細かい#5000くらいまであると完璧です。
必ず荒い目から細かい目へと順番に使っていくことが大切です。いきなり細かい目で磨いても、大きな傷は消えません。段階を踏んで磨いていくことで、美しい仕上がりになります。
Q6. アルミ玉が割れてしまったのですが、修復できますか?
割れてしまった場合でも、修復は可能です。割れた部分の角を手で慎重に内側に折り曲げて、金づちで優しく叩いていきましょう。強く叩きすぎると余計に割れてしまうので、力加減には注意が必要です。
割れた部分を圧縮した後は、紙やすりで削って表面を滑らかにします。割れ目の周囲も含めて広めに削ることで、自然に馴染んでいきます。
ただし、大きく割れてしまった場合は、修復が難しいこともあります。その場合は、残念ですが新しく作り直した方がいいかもしれません。
Q7. つなぎ目を予防する一番のコツは何ですか?
つなぎ目を予防する一番のコツは、最初の成型段階で端っこをしっかり内側に押し込むことです。アルミホイルを丸めるときに、端の部分を指で押し込みながら、他の層としっかり絡み合わせておきましょう。
また、アルミホイルを切らずに使うことも重要です。途中で切れてしまうと、その部分がつなぎ目になってしまう可能性があります。
丸めるときは、綺麗に巻きすぎないことも大切です。表面がボコボコになるくらい、ふわっと巻いていく感じがちょうどいいです。そうすることで、各層が複雑に入り組んで、後から剥離することがなくなります。
Q8. 研磨剤は何を使えばいいですか?
一番のおすすめは「ピカールケア」です。半固形タイプで液だれしないので、初心者でも使いやすいです。ホームセンターやネットショップで簡単に手に入ります。
ピカールケア以外にも、クリーム状の金属磨き用研磨剤がいろいろあります。アルミ用や金属用と書かれているものなら、基本的にどれでも使えます。
研磨剤を使うときは、柔らかい布につけて円を描くように磨いていきます。使いすぎると表面を削りすぎてしまうので、適度な量を使いましょう。
「工作キット」の人気商品をレビュー件数順に楽天でチェック!まとめ
アルミ玉のつなぎ目をなくす方法について、詳しく解説してきました。つなぎ目をなくすための基本は、「カットする」「内側に折り曲げて叩く」「紙やすりで削る」「研磨剤で仕上げる」の4ステップです。
つなぎ目を予防するためには、最初の成型段階で端をしっかり内側に押し込むこと、アルミホイルを切らずに使うこと、綺麗に巻きすぎないことが重要です。
叩くときは、柔らかい場所から始めて徐々に硬い場所へ移動し、最初は優しく、形が整ってきたら少しずつ力を入れていきましょう。全体を均一に叩くことで、つなぎ目が目立たなくなります。
紙やすりは荒い目から細かい目へと順番に使い、最後に研磨剤で仕上げることで、鏡のようにピカピカのアルミ玉が完成します。時間はかかりますが、完成したときの達成感は最高ですよ。
つなぎ目が気になっている方は、ぜひこの記事で紹介した方法を試してみてください。地道な作業の積み重ねが、美しいアルミ玉を作る秘訣です。焦らず、じっくりと時間をかけて作っていきましょう。