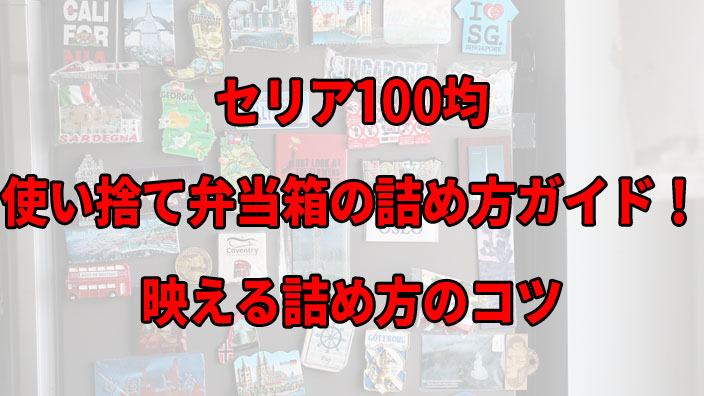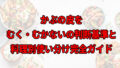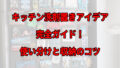セリアの使い捨て弁当箱って、110円でこんなにおしゃれになるなんて驚きますよね。でも、「せっかく買ったのに、どうやって詰めたらきれいに見えるの?」って悩んでいませんか?実は、ちょっとしたコツを知るだけで、まるでお店で買ったお弁当のような仕上がりになるんです。この記事では、セリアの使い捨て弁当箱の種類から詰め方のコツまで、詳しく解説していきます。
セリアの使い捨て弁当箱、レンジ対応だし量丁度いいしで優秀
— 緑野葉 (@AG201910) November 20, 2023
久しぶりにハンバーグ弁当だぜぇ( ・`ω・´) pic.twitter.com/Ayvihhpua0
セリア100均使い捨て弁当箱の魅力とは
セリアの使い捨て弁当箱が人気の理由は、まずそのコストパフォーマンスの良さです。「簡単におしゃれなお弁当が作れて優秀!」と話題になっている通り、110円という価格でありながら、デザイン性と機能性を兼ね備えています。
使い捨て弁当箱の最大のメリットは、何といっても洗い物が出ないことです。食べ終わったらそのまま捨てられるので、特にお出かけ先での利用には最適です。運動会やピクニック、遠足など、年に数回しかない特別なイベントのために新しいお弁当箱を購入するのはもったいないと感じる方も多いでしょう。
また、普通のお弁当箱と違って、その日の気分や用途に合わせて違うデザインを選べるのも楽しさの一つです。子ども向けのかわいいデザインから、大人が使えるシンプルなものまで、豊富な種類が揃っています。
セリアで買える使い捨て弁当箱の種類
紙製ランチボックス
100均で大人気なのが「モールド(型抜き)」タイプのパルプやサトウキビを原料にしたペーパーフードパックです。環境に優しい素材で作られており、上下同じ形のボックスが貝殻のように合わさるバーガーケース型が特徴的です。
紙製のランチボックスは軽量で持ち運びしやすく、ナチュラルな見た目がおしゃれです。ただし、水分に弱いという特徴があるため、汁気の多いおかずを入れる際は注意が必要です。
透明フタタイプ
透明なフタがついたフードパックタイプも人気の商品です。中身が見えるので、お弁当の彩りを活かすことができます。プラスチック製のため、紙製よりも水分に強く、汁気のあるおかずにも対応できます。
電子レンジ対応タイプ
セリアの「マイ・ランチボックスL」はパステルカラーが特徴で、仕切り付きで電子レンジ対応となっています。温かいお弁当を食べたい時に便利で、オフィスでの昼食にも重宝します。
デザイン性重視タイプ
子供向けの「ミモザ&スズラン ランチボックス」や「ディノランド ランチボックス」など、かわいいデザインも豊富です。季節やイベントに合わせた限定デザインも登場するので、定期的にチェックしてみると新しい発見があります。
何度か呟いてるけど、急遽毎日弁当になったご家庭にこれをすすめたい。
— 塩🦠たんたん草🦠 (@sioinsiruko) March 2, 2020
弁当のストレスは弁当箱を洗って乾かして衛生を保つところまでだし、弁当箱は食洗機の中で幅とりまくりなので、私は長期休みの小学生弁当はセリアの使い捨て弁当箱(5枚入り)を愛用しています。おにぎりのアルミも豊富。 pic.twitter.com/qTtNQMbAZ7
基本的な詰め方のコツ
色のバランスを意識する
お弁当をおいしそうに見せる最も重要なポイントは、色のバランスです。赤・黄・緑の3色を基本に、茶色と白を加えた5色を意識すると、自然と栄養バランスも整います。
赤色は、トマトやニンジン、パプリカ、ケチャップを使った料理などで表現できます。黄色は卵焼きやコーン、かぼちゃなど。緑色はブロッコリーやほうれん草、レタスなどの野菜で彩りを加えましょう。
実際に私が娘のお弁当を作る時も、まず色を意識してメニューを考えます。例えば、卵焼き(黄)、ミニトマト(赤)、ブロッコリー(緑)を決めてから、メインのおかずを考えるという流れです。この方法で作ると、見た目も栄養バランスも整ったお弁当になります。
立体感を出す詰め方
平面的に詰めるのではなく、高さを意識した詰め方をすることで、より豪華に見えます。大きなおかずを奥に、小さなおかずを手前に配置し、全体に高低差をつけましょう。
おにぎりや厚みのあるおかずは一番奥に置き、その手前に中くらいのおかず、そして一番手前に薄めのおかずや野菜を配置します。この配置により、お弁当箱を開けた時に全てのおかずが見えて、ボリューム感も演出できます。
隙間を作らない詰め方
お弁当箱の中に隙間があると、移動中におかずが動いて見た目が崩れてしまいます。隙間にはミニトマトやブドウ、枝豆などの小さなおかずを詰めて、全体をしっかりと固定しましょう。
レタスやキャベツなどの葉野菜も、隙間埋めには最適です。彩りも良くなりますし、他のおかずの仕切りとしても機能します。
映える詰め方の具体的テクニック
ワックスペーパーを活用する
紙なので、水分でふやけてしまわないように「ワックスペーパー」や「クッキグシート」は必要なアイテムです。特に紙製の弁当箱を使う場合は、底にワックスペーパーを敷くことで、水分による劣化を防げます。
ワックスペーパーは見た目もおしゃれになるので、一石二鳥です。色や柄の付いたものを選べば、お弁当全体の印象も変わります。
仕切りカップを効果的に使う
100均で手に入るシリコンカップや紙製カップを使えば、汁気を閉じ込めたまま他のおかずと分けることができます。おかず同士の味移りを防ぐだけでなく、見た目にも整然とした印象を与えます。
色とりどりのカップを使い分けることで、お弁当全体がより華やかになります。また、同じ色のカップで統一すると、シンプルで上品な印象になります。
アルミホイルで仕切りを作る
アルミホイルを折っておかず用の仕切りを作ることで、手軽に液漏れ対策をすることが可能です。カップがない時でも、アルミホイルがあれば即座に仕切りを作れるので、覚えておくと便利なテクニックです。
特に汁気の多いおかずには、アルミホイルを二重にして使うと、より確実に液漏れを防げます。
【お弁当】
— 子どもの未来を育む会/Five for earth (@fiveforearth) May 29, 2019
宿泊学習のお弁当は、使い捨ての容器で持っていくということで
セリアで紙の弁当箱を2個100円で買いました。
幼稚園も週2回弁当です。
「お弁当があると朝ごはんにお弁当の残りが食べられるのが楽しみなんだよね」
と言っていました。
我が家はお弁当派です。 pic.twitter.com/g3sWwaRAZn
おかず別の詰め方のポイント
ご飯の詰め方
ご飯は弁当箱の約半分を占める主食なので、詰め方次第で全体の印象が大きく変わります。まず、ご飯を詰める前に弁当箱の底に薄くしょうゆを塗ったり、ふりかけを少し振ったりすると、味にアクセントが付きます。
ご飯は軽く握ってから詰めると、形が崩れにくくなります。また、真ん中を少しくぼませて詰めると、おかずを乗せた時に安定します。白いご飯だけでなく、炊き込みご飯や混ぜご飯にすると、それだけで華やかになります。
メインおかずの配置
から揚げやハンバーグなどのメインおかずは、弁当箱の中で最も目立つ場所に配置しましょう。一般的には、ご飯の隣の一番大きなスペースがベストポジションです。
メインおかずが複数ある場合は、大きさや高さのバランスを考えて配置します。同じ大きさのものを並べるより、大小のメリハリをつけた方が見栄えが良くなります。
副菜の効果的な配置
副菜は隙間を埋めながら、全体の色バランスを整える重要な役割を果たします。特に緑色の野菜は、他の色を引き立てる効果があるので、積極的に取り入れましょう。
ほうれん草のおひたしやいんげんの胡麻和えなど、彩りの良い副菜を弁当箱の角や隙間に配置すると、全体が引き締まって見えます。
セリア使い捨て弁当箱の選び方
用途に合わせた選び方
運動会やピクニックなど屋外で食べる場合は、風に強い密閉性の高いものを選びましょう。セリアやダイソーなどの100均ではこのような液漏れ防止に特化した容器も多く販売されているので、購入時に密閉性をチェックすることが大切です。
一方、オフィスでの昼食なら、電子レンジ対応のものが便利です。温かいお弁当を食べられるので、冬場は特に重宝します。
人数や量に合わせたサイズ選び
大人の男性なら大きめのサイズ、子どもや女性なら小さめのサイズと、食べる人に合わせてサイズを選びましょう。また、がっつり食べたい時とさっぱり食べたい時で、その日の気分に合わせてサイズを変えるのも使い捨てならではの楽しみ方です。
私の経験では、子ども用は小さめのものでも十分ですが、大人用は思っているより大きめのものを選んだ方が、バランス良く詰められます。
デザインで選ぶ楽しさ
セリアの使い捨て弁当箱は、シーズンごとに新しいデザインが登場します。桜の季節には桜柄、ハロウィンの時期にはハロウィン柄など、季節感を楽しめるのも魅力の一つです。
子どもが喜ぶキャラクターもののデザインもありますが、大人が使っても恥ずかしくないシンプルなデザインも豊富です。その日の気分やお弁当の内容に合わせて選べるのは、使い捨てならではの贅沢ですね。
汁漏れ対策と保存のコツ
水分対策の基本
紙製の弁当箱を使う場合、水分対策は特に重要です。汁気の多いおかずは、まず水分をしっかりと切ってから詰めましょう。煮物などは、煮汁を切ってから入れ、必要に応じて片栗粉でとろみをつけると水分が出にくくなります。
また、おかずの下にキッチンペーパーを敷いておくと、余分な水分を吸収してくれます。見た目を気にする場合は、ワックスペーパーの下にキッチンペーパーを敷くという方法もあります。
密閉性を高める工夫
フタがしっかり閉まるタイプや、パッキンが付いて密閉性を高めた商品が存在するので、汁漏れが心配な場合はこうした商品を選びましょう。
さらに安心したい場合は、弁当箱全体をビニール袋に入れてから持ち運ぶという方法もあります。万が一漏れても、カバンの中が汚れる心配がありません。
食中毒予防のポイント
使い捨て弁当箱でも、食中毒予防の基本は同じです。おかずはしっかりと加熱し、よく冷ましてから詰めましょう。特に夏場は、保冷剤を使って温度管理に気を付けることが大切です。
生野菜を使う場合は、よく洗って水分をしっかりと切ってから使います。また、手で直接触れるおにぎりよりも、ご飯をそのまま詰める方が衛生的です。
100均と他の使い捨て弁当箱の違い
コストパフォーマンスの比較
100均の使い捨て弁当箱の最大の魅力は、やはりその価格です。コンビニやスーパーで同様の商品を購入すると、1個200円~500円程度することが多いのに対し、セリアでは110円で購入できます。
頻繁に使わない場合や、子どもの遠足など特別な機会での利用なら、この価格差は大きなメリットです。また、複数の種類を購入して、その日の気分に合わせて選ぶという使い方も、この価格だからこそできることです。
品質とデザインの特徴
価格が安いからといって、品質が劣るわけではありません。セリアの使い捨て弁当箱は、デザイン性も機能性も十分に考慮されています。特にデザイン面では、おしゃれなアイテムが多いと人気なセリアならではの洗練されたものが多く揃っています。
ただし、長時間の保存や、非常に汁気の多いおかずには、より高価な専用容器の方が適している場合もあります。用途に応じて使い分けるのが賢い選択です。
環境への配慮
最近のセリアの使い捨て弁当箱は、環境に配慮した素材で作られているものが増えています。従来のプラスチック製品に比べて、紙製やバイオプラスチック製の商品が多く展開されています。
使い捨て商品ではありますが、適切に分別して廃棄すれば、環境負荷を最小限に抑えることができます。また、年に数回の利用なら、繰り返し洗って使う弁当箱よりも、トータルでの環境負荷は少ない場合もあります。
おしゃれに見せる盛り付けアイデア
カフェ風の盛り付けテクニック
サンドイッチを作る時は、具材の層を意識すると、カット面が美しく見えます。レタス、トマト、ハム、チーズなどを順番に重ねて、最後にピックで固定すると、まるでカフェで出てくるような仕上がりになります。
おにぎりも、海苔を巻く位置を工夫したり、ゴマを振ったりすることで、いつもと違った印象になります。三角形だけでなく、俵型や丸型など、形を変えるだけでもバリエーションが広がります。
色彩を活かした配置術
暖色系(赤、オレンジ、黄色)のおかずと寒色系(緑、青、紫)のおかずをバランス良く配置すると、視覚的に美しく見えます。また、同系色でまとめることで、統一感のある上品な印象も演出できます。
例えば、黄色い卵焼き、オレンジ色のニンジンのグラッセ、赤いミニトマトを一緒に配置すると、暖かい印象のお弁当になります。一方、緑のブロッコリー、紫のキャベツ、白いカリフラワーを組み合わせると、クールで洗練された印象になります。
季節感を演出するアイデア
春なら桜でんぶやピンク色のかまぼこ、夏なら枝豆やとうもろこし、秋なら栗や柿、冬なら大根や白菜など、季節の食材を積極的に使うことで、その時期らしい弁当になります。
また、弁当箱自体も季節に合わせて選ぶと、より統一感が出ます。セリアでは季節限定のデザインも多く出るので、タイミングを見て購入するのがおすすめです。
今日の相棒さん弁当。焼鮭入れたのに、ごはんにシャケフレーク挟んだ気がする…🐟まあいいか この使い捨て容器(セリア)の形、詰めやすいのでこの形のベント箱欲しい ストロー廃止ニュースを最近よく聞くので、洗って使えるストローも買った🥤 pic.twitter.com/neQ71a8ofY
— nao_mekko (@naomekkotamori) August 10, 2018
子供が喜ぶ詰め方のコツ
カラフルで楽しい見た目作り
子どもは見た目で食べ物の好き嫌いを判断することが多いので、カラフルで楽しい見た目作りが重要です。野菜が苦手な子でも、可愛くカットしたり、好きなキャラクターの形にしたりすることで、食べてくれることがあります。
私の娘も野菜が苦手でしたが、ニンジンを星型に、キュウリを花型にカットして入れたところ、「可愛い!」と言って完食してくれました。少し手間はかかりますが、子どもの喜ぶ顔を見ると、その苦労も報われます。
食べやすいサイズと配置
子どもの小さな手でも食べやすいように、一口サイズにカットすることが大切です。また、食べる順番も考慮して配置すると、子どもが迷わずに食べ進められます。
好きなおかずを最初に見える場所に配置し、苦手なものは好きなものの陰に隠すように配置すると、全体を食べてくれる確率が上がります。
栄養バランスを考慮した工夫
見た目の楽しさだけでなく、栄養バランスも重要です。主食、主菜、副菜をバランス良く配置し、特に不足しがちな野菜を多めに入れるよう心がけましょう。
ただし、あまりにも多くの種類を入れすぎると、子どもが混乱してしまうことがあります。3〜5品程度に絞って、それぞれをしっかりと美味しく作る方が効果的です。
イベント別おすすめ使い分け方法
運動会での活用法
運動会では、家族全員分のお弁当を準備することが多いので、人数分の弁当箱を用意するのは大変です。そんな時は、大きめの使い捨て弁当箱を使ってシェアするスタイルがおすすめです。
また、運動会では子どもたちが汗をかいているので、さっぱりとした味付けのおかずを多めに入れると喜ばれます。おにぎりは塩分を少し多めにして、水分補給を促進する効果も期待できます。
ピクニックでの楽しみ方
ピクニックでは、屋外で食べることを前提に、風で飛ばされにくい重めのおかずを選びましょう。また、手で食べやすいサンドイッチやおにぎりを中心にすると、食べやすさも向上します。
景色の良い場所で食べることが多いピクニックでは、弁当箱のデザインにもこだわりたいものです。セリアには自然を感じられるナチュラルなデザインの弁当箱もあるので、雰囲気に合わせて選んでみてください。
遠足での準備ポイント
遠足では、子どもが自分で食べることを考慮して、食べやすさを最優先に考えましょう。蓋が開けやすく、中身がこぼれにくい構造の弁当箱を選ぶことが大切です。
また、遠足では歩くことが多いので、消化の良いものを中心に、エネルギーになる炭水化物を多めに入れると良いでしょう。ただし、あまりにも量が多いと重くなってしまうので、適度な量に調整することも必要です。
失敗しがちなポイントと対策
よくある詰め方の失敗例
最もよくある失敗は、隙間を作りすぎることです。隙間があると移動中におかずが動いてしまい、見た目が崩れてしまいます。また、汁気の多いおかずを直接弁当箱に入れてしまい、他のおかずと混ざってしまうという失敗もよく見られます。
色のバランスを考えずに詰めてしまうと、茶色一色の地味な弁当になってしまうことも。これらの失敗は、事前に計画を立てることで避けることができます。
時間短縮のための準備術
忙しい朝に弁当を作るのは大変ですが、前日の夜に準備できることは済ませておくと楽になります。野菜をカットして水にさらしておく、おかずの一部を作り置きしておく、弁当箱を準備しておくなど、できることから始めましょう。
また、冷凍食品を上手に活用することも時短のコツです。最近の冷凍食品は品質が向上しているので、手作りおかずと組み合わせて使えば、時間を節約しながらも美味しい弁当が作れます。
食中毒を防ぐ注意点
特に夏場は食中毒のリスクが高まるので、注意が必要です。おかずはしっかりと加熱し、よく冷ましてから詰めることが基本です。また、素手で食材を触らないよう、清潔な箸やトングを使用しましょう。
保冷剤の使用も効果的ですが、弁当箱が結露して水分が付くことがあるので、タオルで包むなどの工夫も必要です。また、作ってから食べるまでの時間が長い場合は、より慎重な管理が求められます。
便利グッズとの組み合わせ活用法
今月も無事にお弁当が完成した!!
— みみ🌸 (@mmk10123) May 20, 2025
セリアのおにぎり型のおかげで可愛くできたけどおかずの入れ方が下手でハートのおにぎり潰れちゃった😇
完食してくれたらいいな pic.twitter.com/ayBentCeNj
100均で揃えられる便利アイテム
セリアには弁当作りに便利なグッズがたくさんあります。野菜の型抜き、おにぎりの型、シリコンカップ、ピックなど、これらのアイテムを使うことで、より手軽におしゃれな弁当が作れます。
特におすすめなのが、野菜の型抜きです。ニンジンやダイコンを可愛い形にカットできるので、子どもが喜ぶだけでなく、大人の弁当にも華やかさをプラスできます。
保冷・保温グッズとの相性
使い捨て弁当箱は薄いので、保温性はあまり期待できません。温かい弁当を食べたい場合は、保温バッグや保温ジャーとの組み合わせを検討しましょう。
逆に夏場は、保冷剤と保冷バッグの組み合わせが必須です。ただし、結露による水分でせっかくの弁当が水っぽくなってしまうことがあるので、タオルで包むなどの対策を忘れずに。
持ち運び用バッグの選び方
使い捨て弁当箱は軽量ですが、その分、移動中に中身が動きやすいという特徴があります。クッション性のある弁当袋や、仕切りのついたバッグを選ぶと、弁当の形を保ちながら持ち運べます。
また、汁漏れが心配な場合は、防水性のある素材のバッグを選ぶか、弁当箱をビニール袋で包んでから入れると安心です。
よくある質問(FAQ)
Q1: セリアの使い捨て弁当箱は電子レンジで使えますか?
セリアの使い捨て弁当箱には、電子レンジ対応のものとそうでないものがあります。「マイ・ランチボックスL」はパステルカラーが特徴で、仕切り付きで電子レンジ対応となっています。商品パッケージに電子レンジマークがあるかどうか確認してから購入しましょう。
紙製の弁当箱は基本的に電子レンジでは使用できません。温め直したい場合は、別の容器に移し替える必要があります。プラスチック製のものでも、耐熱温度が記載されているので、それを超えない範囲で使用してください。
Q2: 汁漏れしにくい詰め方のコツはありますか?
汁漏れを防ぐには、まず汁気の多いおかずの水分をしっかりと切ることが基本です。100均で手に入るシリコンカップや紙製カップを使えば、汁気を閉じ込めたまま他のおかずと分けることができます。
さらに、アルミホイルを折っておかず用の仕切りを作ることで、手軽に液漏れ対策をすることが可能です。特に汁気の多いおかずには、アルミホイルを二重にして使うと、より確実に液漏れを防げます。
底にワックスペーパーやクッキングシートを敷いておくことも効果的です。見た目もおしゃれになりますし、万が一水分が出ても弁当箱への影響を最小限に抑えられます。
Q3: どのくらいの量を詰めるのが適切ですか?
弁当箱の容量の8割程度を目安に詰めるのが理想的です。詰めすぎると蓋が閉まらなくなったり、移動中におかずが崩れたりしてしまいます。逆に少なすぎると、見た目が寂しくなってしまいます。
大人の男性なら700ml〜900ml、女性なら500ml〜700ml、子どもなら300ml〜500ml程度が一般的な目安です。ただし、その日の活動量や食欲に合わせて調整することも大切です。
Q4: 前日に作り置きしても大丈夫ですか?
基本的には当日の朝に作ることをおすすめしますが、一部のおかずは前日に準備することができます。きんぴらごぼうや煮物などの火を通したおかずは、冷蔵庫で保存すれば翌日でも使えます。
ただし、生野菜や卵料理、マヨネーズを使ったおかずは傷みやすいので、当日に作る方が安全です。また、前日に作ったおかずも、朝にもう一度火を通してから詰めると、より安心です。
Q5: 見た目をおしゃれにするコツを教えてください
色のバランスが最も重要です。赤・黄・緑の3色を基本に、茶色と白を加えた5色を意識すると、自然と栄養バランスも整い、見た目も美しくなります。
また、高さを意識した詰め方も効果的です。大きなおかずを奥に、小さなおかずを手前に配置し、全体に高低差をつけることで立体感が生まれます。100均で買えるピックや型抜きを使って、ちょっとした装飾を加えるのもおすすめです。
Q6: 子どもが完食してくれるコツはありますか?
子どもが好きなおかずを一つは必ず入れることが大切です。そして、苦手なものは小さくカットして、好きなものの陰に隠すように配置すると、気づかずに食べてくれることがあります。
野菜も型抜きを使って可愛い形にしたり、キャラクターを模した配置にしたりすると、興味を持って食べてくれます。また、量は少し控えめにして、「全部食べられた!」という達成感を味わわせることも重要です。
Q7: 夏場の食中毒対策はどうすればいいですか?
夏場は特に注意が必要です。まず、おかずはしっかりと加熱し、よく冷ましてから詰めることが基本です。保冷剤を使って温度管理に気を付け、できるだけ涼しい場所で保管しましょう。
生野菜を使う場合は、よく洗って水分をしっかりと切ってから使います。また、作ってから食べるまでの時間を短くすることも大切です。朝作ったお弁当は、お昼には食べきるようにしましょう。
Q8: 100均の弁当箱とコンビニ弁当の容器、どちらがいいですか?
用途によって使い分けるのがおすすめです。100均の弁当箱は、デザイン性が高く、価格も安いので、頻繁に使わない場合や特別なイベントでの利用に適しています。
一方、コンビニ弁当の容器は、密閉性や保温性に優れているものが多いので、汁気の多いおかずを入れる場合や、長時間持ち運ぶ場合には適しています。どちらも使い捨てなので、その日の用途に合わせて選ぶと良いでしょう。
「使い捨て弁当箱 おしゃれ」の人気商品をレビュー件数順に楽天でチェック!まとめ
セリアの使い捨て弁当箱は、110円という低価格でありながら、デザイン性と機能性を兼ね備えた優秀なアイテムです。年に数回しかない特別なイベントや、洗い物を減らしたい時に大変便利で、種類も豊富なので用途に合わせて選ぶことができます。
詰め方のコツとして最も重要なのは、色のバランスを意識することです。赤・黄・緑の3色を基本に、立体感を出す配置を心がければ、まるでお店で買ったような仕上がりになります。汁漏れ対策には、シリコンカップやワックスペーパーを活用し、食中毒予防のために適切な温度管理を行うことも大切です。
子どもが喜ぶ弁当を作るには、カラフルで食べやすいサイズにすることがポイントで、大人向けには季節感を演出したり、カフェ風の盛り付けを取り入れたりすることで、より魅力的な弁当になります。
100均の便利グッズと組み合わせることで、手軽におしゃれな弁当作りが楽しめるので、ぜひ色々な方法を試してみてください。使い捨てならではの気軽さを活かして、毎回違うデザインや詰め方に挑戦するのも楽しいものです。